「高所作業に資格は必要なの?」
「高所作業の資格はどんなものがあるの?」
こんな疑問にお答えする記事です。
高所作業は危険を伴う作業であり、適切な資格を取得し知識と技術を学ぶことが不可欠です。本記事では、高所作業に関連する主な資格について詳しく解説します。
様々な高所作業に必要な資格を一覧で紹介し、受講対象者、講習内容、費用、難易度などが一目で分かるように解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
 目次
目次
高所作業とは?

高所作業は、労働安全衛生法によって「2メートル以上の高さで行う作業」と定義されています。
この基準は、墜落などのリスクが高まる高さで行われる作業を対象としており、事故を防ぐための安全対策が求められます。
高所作業が必要となる工事現場
高所作業は以下のような工事現場で多く見られます。
- 橋梁工事での高所作業
- 高架道路の建設や補修
- 足場を使用した建設工事
- 法面工事での斜面での作業
- タワークレーンの操作
このような高所作業は、建設現場の様々な場面で必要となる作業ですが、同時に危険が伴う作業でもあります。
災害を起こさないためには、教育や講習で正しい知識を身に着け、安全対策を徹底し、事故防止に努めることが重要です。
高所作業は災害が多い
高所作業では転落や転倒などの事故が多く発生していますが、以下のような事例が代表的です。
- 屋根や足場からの転落
- 脚立からの転倒
- 高所作業車やゴンドラからの落下
- 資材や工具の落下事故
上記は、教育や講習を受講し正しく作業していても、十分にありうる事故です。
事故が起こる原因は、高所作業の知識不足だけでなく、慢心、焦り、不注意、疲労、天候など、様々な要因が複雑に絡み合っているからです。
高所作業の安全確保には、安全意識の向上、作業環境の整備、安全装備の適切な使用、リスクアセスメントの実施、標準作業手順書の作成、緊急時の対応訓練といった、多角的な取り組みが重要です。
ちなみに下記の記事では、高所作業の年齢制限や高所作業の注意点をお伝えしています。労働災害を減らす方法が分かりますのでこちらも合わせてご覧ください。
高所作業に必要な資格の種類

高所作業に必要な主な資格は下記のとおりです。
- フルハーネス特別教育
- 足場特別教育
- 足場の組立て等作業主任者技能講習
- 高所作業車運転特別教育
- 高所作業車運転技能講習
- ロープ高所作業特別教育
- ゴンドラ取扱特別教育
- 玉掛け技能講習
玉掛け作業は高所作業ではないですが高所作業と関連性が高いため、今回ご紹介しています。
それでは、詳しく見ていきましょう。
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
高さ2メートル以上で作業床を設けることが困難な場所において必要となる、落下防止用の安全装置を、フルハーネス型墜落制止用器具といいます。
この安全装置を正しく使用するための教育が、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育です。
2019年2月以降は、原則としてフルハーネス型の落下防止器具の使用が義務付けられました。
教育の内容は、フルハーネス型墜落制止用器具の構造や使用方法、関連法規などについて学びます。試験ではなく学科講習と実技講習の受講によって修了となります。
| 受講資格 | なし |
| 受講料金 | 1万〜1万2千円程度 |
| 講習時間 | 学科科目:4時間30分 実技科目:1時間30分 |
| 試験 | なし(講習の受講のみで修了) |
| 難易度 | やさしい |
足場特別教育
足場特別教育は、つり足場と張出し足場を除く全ての足場の組立て、解体、変更作業に従事する労働者に必要です。
足場の高さに関係なく受講が義務付けられており、低い足場や脚立足場でも必要となります。建設現場で足場を組む、解体する、変更する作業に従事する場合はもちろん、移動式足場を使用する際にも受講が必要です。
| 受講資格 | なし |
| 受講料金 | 1万円程度 |
| 受講時間 | 学科科目のみ7時間 |
| 試験 | なし |
| 難易度 | やさしい |
足場の組立て等作業主任者技能講習
足場の組立て等作業主任者技能講習は、高所での足場作業の安全管理を担う作業主任者になるために必要です。高さ5メートル以上の足場の組立て、解体、または変更の作業を行う際に必要となります。
| 受講資格 | ・満21歳以上かつ、足場の組立、解体、変更作業に3年以上従事した経験 ・満20歳以上で、大学、高専、高校、中学において土木、建築または造船に関する学科を専攻し、その後2年以上足場作業に従事した経験がある |
| 受講料 | 1万〜2万円程度 |
| 講習時間 | 学科:7時間、2日目6時間(保有資格、経験により異なる) |
| 試験 | あり |
| 難易度 | やさしい |
高所作業車運転特別教育
高所作業車運転特別教育は、作業床高さ10メートル未満の高所作業車の運転に必要です。
高所作業車運転特別教育の講習内容は、高所作業車の構造や取扱い方法、原動機に関する基礎知識、運転に必要な一般的事項、関係法令の理解、そして実際の操作技術の習得です。
高所作業車を安全かつ効率的に運転するために必要な知識と技能を、総合的に学べるようになっています。
| 受講資格 | 18歳以上 |
| 受講料金 | 1万〜1万5千円程度 |
| 講習時間 | 学科6時間以上、実技3時間以上 |
| 試験 | なし |
| 難易度 | やさしい |
高所作業車運転技能講習
高所作業車運転技能講習は、作業床の高さが10メートル以上の高所作業車を運転する際に必要です。この講習では、高所作業車の構造や取扱い方法、原動機に関する基礎知識、運転に必要な一般的事項、そして関係法令について学びます。
この資格は、建設現場や電気工事、看板設置など、高所での作業が必要な様々な業種で求められており、取得すると作業の安全性向上と効率化が期待できます。
| 受講資格 | 18歳以上 |
| 受講料金 | 3万4千円程度 |
| 講習時間 | 12時間〜17時間(保有資格により異なる) |
| 試験 | 学科試験、実技試験あり |
| 難易度 | やさしい |
ちなみに、高所作業車運転特別教育、高所作業車運転技能講習の詳しい概要は下記の記事で解説しています。
講習内容や注意点、実施機関まで分かりますので、受講予定の方は参考にしてみてください。
ロープ高所作業特別教育
ロープ高所作業特別教育は、足場の設置が困難な高所でロープを使用して作業を行う際に必要です。
この教育では、ロープ高所作業の基本知識や技術、メインロープの特性と取り扱い方、労働災害の防止策、関連法規について学びます。また、実際にロープ高所作業を行う方法や、使用する機材の点検手順も実技で習得できます。
| 受講資格 | 18歳以上 |
| 受講料金 | 1万4千円程度 |
| 講習時間 | 学科4時間、実技3時間 |
| 試験 | なし |
| 難易度 | やさしい |
ゴンドラ取扱特別教育
ゴンドラ取扱い業務特別教育は、高層ビルや橋梁、ダムなどの大型構造物の外壁工事で必要です。
教育の内容は、ゴンドラの構造や機能に関する基本知識、操作に必要な電気の知識、関連法規です。実技では、実際のゴンドラ操作方法や作業時の合図なども習得します。
この特別教育を受講することで、高所での安全な作業遂行に不可欠な知識と技能が身につき、ゴンドラを適切に扱えるようになります。
玉掛け技能講習
玉掛け技能講習は、つり上げ荷重1トン以上のクレーン、デリック、移動式クレーンを使用して荷を吊り上げる作業に必要です。
この講習では、クレーンの基本知識、力学、玉掛けの方法、関係法令について学び、実際の玉掛け作業の実技も習得します。
玉掛け作業はクレーンなどを使用して荷物を吊り上げる作業であり、厳密には高所作業ではありません。しかし、高層建築の建設現場では、玉掛け作業と高所作業が同時に行われることがあります。
| 受講資格 | 18歳以上 |
| 受講料金 | 4万円程度 |
| 講習時間 | 学科9時間、実技6時間 |
| 試験 | 学科試験、実技試験あり |
| 難易度 | やさしい。しっかり講習を受ければ修了試験に合格できます |
また、下位資格に玉掛け特別講習があります。こちらは、学科6時間、実技4時間で、講習料金は2万円程度です。
下記の記事でも玉掛け技能者について詳しく解説しています。クレーン作業との関係性や、各業界の玉掛け資格が必要な場面をご紹介しているので、ぜひ合わせてご覧ください。
教育や講習を受講する上での注意点
教育や講習を受講する際に注意しておきたいことがいくつかあります。
ここで注意点をお伝えするので、実際に教育や講習を受講する際の参考にしてみてください。
事前準備しておく
講習の内容や目的を事前に把握し、関連する基礎知識を復習しておくことで、より深い理解が可能になります。
また、自分の学習目標を明確にしておくことで、講習中に重要なポイントを逃さず、効率的に学ぶことができます。可能であれば、事前に質問事項をまとめておくのも良いでしょう。
受講中は真面目に話を聞く
たとえ難易度の低い教育や講習でも、講師の話をしっかり聞き、質問があるときはためらわずに聞くことが大切です。他の参加者と話すことで、異なる考えや経験から新しい気づきを得られることもあるでしょう。
ノートを取るときは、全てを書き写すのではなく、重要なポイントや自分が気づいたことを中心にメモすることが大事です。図や表を使ったり、大事な言葉を強調したりすることで、後で見返しやすくなります。
疑問があれば質問し、講師からのフィードバックをもらうことで、自分の理解度を確認できます。他の人の質問にも耳を傾けることで、自分では気づかなかったことを学べるでしょう。
修了証は大切に保管
修了証は、教育や講習を受けたことを証明する重要な書類であり、自分の努力と成果を示すものでもあります。今後のキャリアにおいても重要ですので、しっかりと保管することが大切です。
修了証は履歴書や職務経歴書に記載する際に必要となる場合があります。特に専門的な資格やスキルを求められる職場では、修了証があなたの能力を裏付ける重要な証拠となります。
また、工事現場で修了証の提示を求められることもあります。取り出しやすい場所に保管しておくことも大切です。
高所作業に関するQ&Aコーナー
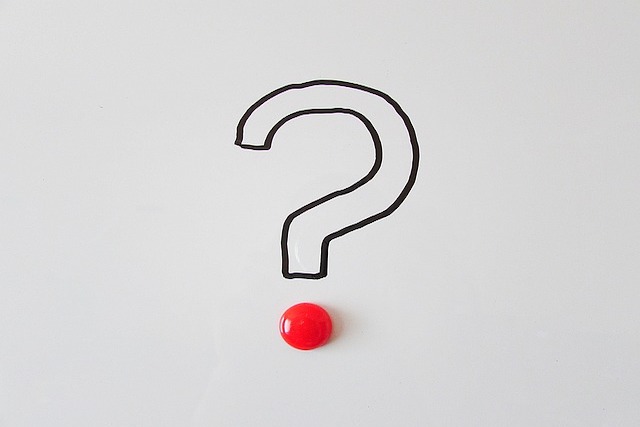
これから高所作業を行う方が疑問に思うことを、Q&A形式で解説していきますのでご覧ください。
「高所作業で最も気をつけるべきことは何ですか?」
【回答】高所作業で最も気をつけるべきことは「墜落防止」です。
特に以下の点に特に注意を払いましょう。
- 適切な墜落制止用器具(安全帯やフルハーネス)の着用と正しい使用
- 作業床や足場の安全確認(手すりの有無、床面の安定性など)
- 天候条件の確認(強風や雨などの危険な状況を避ける)
- 作業範囲の明確化と逸脱の防止
- 工具や資材の落下防止対策
- 定期的な休憩と体調管理
- 同僚とのコミュニケーションの維持
安全第一の意識を持って作業に臨みましょう。
「天候の悪い日の高所作業は避けるべきですか?」
【回答】基本的に、悪天候時の高所作業は避けるべきです。
作業開始前に天候を確認し、悪化が予想される場合は作業の延期や中止を検討するか、作業主任者などに指示をもらうようにしましょう。
また、作業中も定期的に天候の変化に注意を払い、状況に応じて速やかに対応することが重要です。
安全が確保できない場合は、躊躇せずに作業を中止することが大切です。
「高所作業の資格は何から取得すべきですか?」
【回答】高所作業を行う上で一番基本的な教育である、「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」を受講しましょう。
次に、「高所作業車運転特別教育」、「高所作業車運転技能講習」を受講してステップアップしていくのが王道です。
「フルハーネスをうまく装着できません」
【回答】取扱説明書を見て、手順に従って装着することが基本です。また、他の作業者から正しく装着できているかチェックしてもらいましょう。
肩ベルトは落下時の安全を確保するため、しっかりと締めることが重要。背中の真ん中あたりにある輪っかの位置は、肩甲骨の高さに調整し落下時の姿勢を適切に保つようにします。
胸ベルトと腿ベルトも同様にしっかりと締め、特に腿ベルトの緩みは危険なので注意が必要です。
私も経験がありますが、高所作業初心者の場合、フルハーネスの装着には少し苦労するかもしれません。
しかし、適切に装着できていないと器具の効果を発揮できない可能性があります。きちんと装着できているか、同僚に確認してもらうことが重要です。
まとめ:高所作業の資格を取得して安全に作業しよう

高所作業は危険を伴う作業ですが、適切な資格を取得し、安全対策を徹底することで、事故のリスクを大幅に減らせます。
本記事では、それぞれ特定の高所作業に対応したものをご紹介しました。自分の仕事内容や将来のキャリアプランに合わせて、必要な資格を取得しておきましょう。
GARDEN-JOBは、造園・外構・土木に特化した求人情報サイトです。登録は無料、3分程度で完了します。入社お祝い金最大5万円も用意していますので、関東、関西、東海エリアでお仕事をお探しの方は、ぜひGARDEN-JOBを有効活用してください。



























