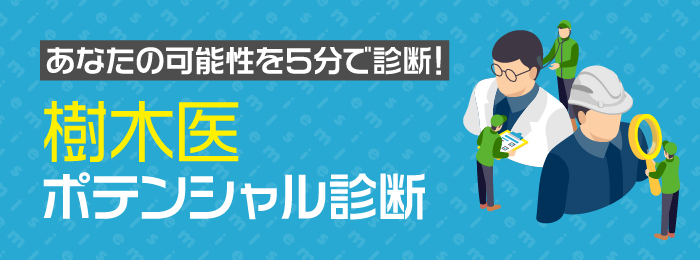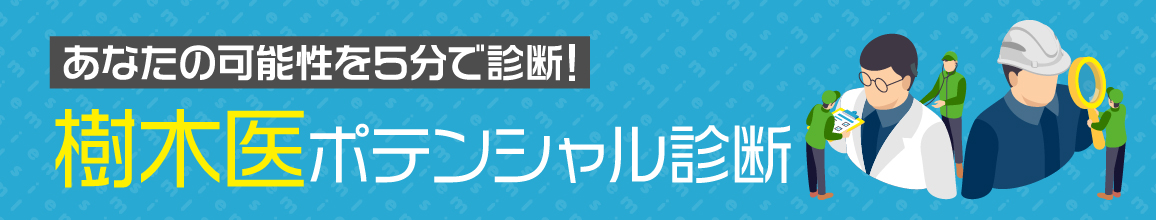「樹木医になるにはどうすればいいの?」
「専門学校や大学に行ってなくてもなれるの?」
「樹木医になったらどんなところで働けるのかな?」
こんな疑問に答える記事です。
樹木医は、木の病気を診断し、治療やケアを行う専門家です。
自然環境への関心が高まる現代、その役割はますます重要になっています。
本記事では、樹木医になるための主な道のりや、資格取得後の働き方についてわかりやすくご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
 目次
目次
樹木医になるには?

樹木医は、樹木の健康状態を診断し適切なケアを行う専門家です。まさに木の医者と言って良いでしょう。
さっそく樹木医になる方法を詳しくお伝えしていきましょう。
受験資格と必要な実務経験
樹木医の受験資格には、
「樹木医補の資格を所持し、一定期間(通常は1年以上)の実務経験があること」
「関連分野で5年以上の実務経験を有すること」
が求められます。
対象となる実務経験は、造園・園芸・林業・自治体の緑化関連業務など幅広く認められています。
受験前に資格要件や経歴証明の提出書類をしっかり確認して準備しましょう。
樹木医補になるには
樹木医補になるためには、公益財団法人・日本緑化センターが認定する大学で、所定のカリキュラム(必要単位)を履修し修了する必要があります。
単位修得後、大学側が推薦申請を行い、申請が認められれば晴れて樹木医補として登録されます。
認定大学等一覧は「一般財団法人 日本緑化センター」から確認できます。
樹木医補から樹木医へのステップアップ
樹木医補として認定された後は、現場での実務経験を1年積みながら、樹木医の資格取得を目指します。
必要とされる実務年数を満たした後、正式に樹木医試験に望むという形です。
現場で多様な経験やスキルを習得することで、試験対策はもちろん、今後の樹木医としての活躍にも大きく役立つでしょう。
樹木医と樹木医補の違い
樹木医は高度な専門知識と実務経験を持ち、樹木診断や治療を独自に実施できる資格者です。
一方、樹木医補は治療や診断を単独で行うことはできませんが、樹木医の指導や補助のもとで実務経験を積むことができます。
役割と権限の違いを理解しておきましょう。
樹木医試験の概要

樹木医試験は、第一次審査(筆記試験)と、第二次審査(研修)に分かれています。
筆記試験では専門知識の習得度や実務経験が問われ、面接では応用力や現場での対応力が評価されます。
第一次審査(筆記試験)
- 択一式(90分・35問)
樹木医に必要な一般教養(倫理含む)、専門分野、高校生物レベルの知識などが出題されます。
- 論述式(90分・3問)
樹木の診断・治療・管理などに関するテーマが出題され、各問400字程度で記述します。知識や技術に加え、文章能力や説明能力が問われます。
第二次審査(樹木医研修)
筆記試験合格後、2週間程度の研修(講義・実習・筆記・面接)を受け、適性や現場力が総合的に審査されます。
具体的には、樹木の分類、生理、生態、構造と機能、制度などの16科目についての筆記試験、樹種の識別に関する適性試験、面接試験が行われます。
試験対策や合格率などに関しては、下記の記事で詳しく解説していますので、こちらも合わせてご覧ください。
資格取得後のキャリアと活躍できる就業先

樹木医や樹木医補の資格を取得した後は、幅広い分野で活躍できます。
公的機関や民間企業、自治体の緑化事業、環境保全活動など多様な就業先があります。
自分の専門性を活かして、社会や地域の緑化・保全に貢献できる職業です。
樹木医・樹木医補の主な就業先
樹木医・樹木医補の主な就業先は下記のとおり。
- 自治体の緑化部門
- 公園管理会社
- 造園業
- 林業
- 植物園
- 環境コンサル会社など
また、都市緑化・街路樹の維持管理や、文化財の樹木保護活動に携わることも可能です。
樹木医になりさえすれば、自分の興味や適性に応じて、多様な環境でキャリアを積めます。
樹木医の知識と経験を活かして、樹木の保全・診断に関わる仕事を探そう!
社会で活かせる専門性と今後の展望
樹木医の専門性は、都市緑化の推進や気候変動対策、生物多様性の保全など、これからの社会にますます求められる分野です。
今後は更なる技術革新やデータ活用が進み、樹木医の活躍の場も広がっています。
自然と共生する持続可能な社会づくりに寄与できる重要な人材として、多くの活躍が期待されています。
地域貢献・緑化活動への関わり方
樹木医や樹木医補は、地域の緑化計画や市民参加型の植樹イベント、自然観察のガイドなど、地元の環境保全活動に深く関わることができます。
学校や自治体、NPOと連携し、専門知識を活かした啓発活動や地域コミュニティへの技術提供を行うことも可能です。
社会的な信頼やつながりを築きながら、身近な自然環境の維持・向上に貢献できます。
樹木医Q&Aコーナー

ここからは、樹木医や樹木医補を目指す方のよくある疑問について紹介します。
これから資格取得を考える方や、不安を抱いている方はぜひご覧ください。
他業種からでも樹木医を目指せますか?
他業種からでも樹木医を目指すことは十分に可能です。
造園業や農林業の現場で実務経験5年を積むことで受験資格が得られます。
市民講座や通信講座を活用して基礎知識を学ぶこともできます。
ただし、5年の実務経験が必要ですので、社会人から樹木医に転職したい方は、早めに造園業や農林業への転職準備を進めると良いでしょう。
実務経験が足りない場合はどうすればいい?
受験に必要な実務経験年数が不足している場合は、造園会社や公園管理、自治体の関連部署などで働きながら実績を積みましょう。
また、ボランティア活動への参加や、樹木医が携わる工事のサポートなども経験として認められる場合があります。
あせらず着実に実務経験を積んでいけばOKです。
女性でも樹木医になれますか?
もちろん女性でも樹木医になれます。
実際に活躍している女性樹木医も増えており、体力面での不安があっても、工夫次第で十分業務をこなせます。
多様な働き方や、女性を支援するネットワークも広がっていますので、安心してチャレンジしてください。
今後の制度変更や最新情報が知りたい
樹木医の資格制度は社会情勢や技術の進展により、変更や見直しが行われることがあります。
最新情報は日本緑化センターや各大学の公式サイトなどで随時発表されていますので、定期的なチェックがおすすめです。
セミナーや説明会にも積極的に参加し、最新情報を得るのも良いでしょう。
まとめ:自分に合ったルートで樹木医を目指そう

樹木医になるためには複数のルートが存在し、学歴や経験に応じて最適な方法を選ぶことが重要。
自分の状況や将来設計を踏まえて計画的に準備を進めましょう。
専門知識や実務経験を積み、社会で貢献できる樹木医を目指して、一歩ずつ着実にステップアップしてください。
なお、造園・園芸・外構・土木職人専門の転職求人サイト「GARDEN-JOB」では、関西・東海・関東エリアの求人情報を掲載中。
正社員・契約社員・アルバイトの造園職人や庭師、外構職人や、現場を監督していく施工管理職など、造園・外構業界専門の求人情報が充実しています。
GARDEN-JOBに会員登録をすると企業とのメッセージのやりとりや応募履歴の確認など便利な機能が利用できますので、ぜひご活用ください。