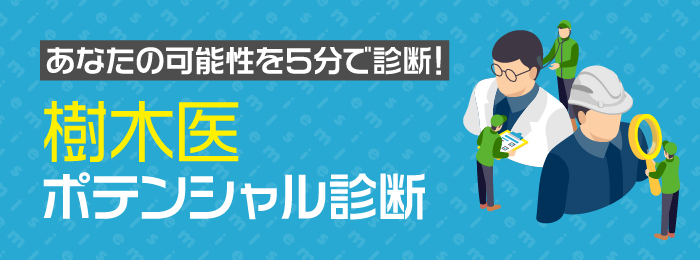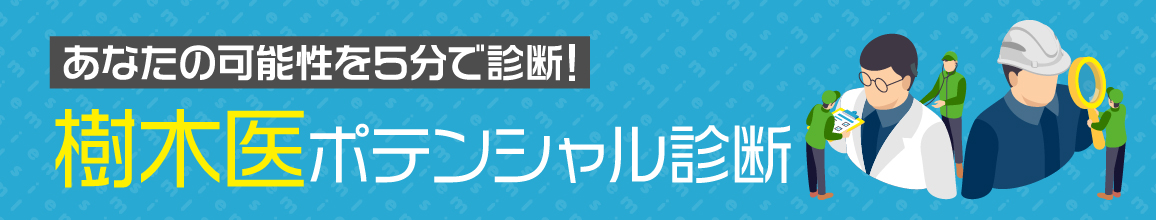「樹木医の難易度と受験資格を知りたい」
「試験勉強はどんなことをすれば合格率が上がるかな?」
こんな疑問に答える記事です。
樹木医を目指す方にとって、試験概要や勉強方法はとてもきになるところではないでしょうか。
本記事では、樹木医の難易度、受験資格、勉強方法をお伝えするのでぜひ最後までご覧ください。
 目次
目次
樹木医とは?
樹木医は、樹木に関する医学、菌類、動物、土壌に関する深い知識と技術を持つ専門家です。
街路樹や公園の樹木を守り、病気になった樹木を治療することで、木が本来持っている生命力を回復させる重要な役割を担っています。
樹木医の仕事内容
樹木医の主な仕事内容は、樹木の病気の診断、治療、病気予防の指導です。樹木の健康を維持するために、様々な病害虫や環境汚染に対する対策を講じます。
造園計画や緑化計画にコンサルタントとして関与し、都市や地域の緑化を支援することもあります。
そのため、樹木に関する基本的な知識から専門的な知識まで幅広く習得する必要があります。知識と経験を積めば、樹木が直面する様々な問題に対処し、持続可能な環境を作り出すことが可能になります。
樹木医は、自然環境の保護と持続可能な都市開発に貢献する重要な存在であり、生活環境をより豊かにするために欠かせない専門家として活躍する重要なポジションと言えます。
樹木医補との違い
樹木医補は、樹木医の補助的な役割を担う資格です。
樹木医補になるには、樹木医補資格養成機関の認定を受けた大学等で、所定の科目を履修、修了しなければなりません。
まずは、樹木医補資格養成機関に在学し、樹木医補を目指すのが王道です。
樹木医の試験概要
樹木医の試験概要を下記の項目で解説します。
- 受験資格
- 難易度と合格率
- 試験日程と料金
- 試験の内容
1つずつ見ていきましょう。
受験資格
樹木医の資格を取得するには、樹木の保護や管理・診断・治療に関する実務経験が必要です。
- 樹木医補の認定がされていない人:実務経験7年以上
- 樹木医補認定を受けている人 :実務経験1年以上
まずは樹木医補になり、実務経験を1年積んでから試験に挑戦するのが近道です。
難易度と合格率
樹木医試験の合格率は、約20%です。
樹木医は豊富な実務経験と専門知識が求められ、業務経験が7年以上必要ということもあり試験の内容も難しくなっています。
また、第1次試験で100〜110人に選抜されなければ、第2次試験に進めないため、樹木医試験の難易度は非常に難易度が高いと言えるでしょう。
日程と料金
樹木医試験は下記の流れで行われます。
- 選抜試験で受講者を選定(100〜110人)
- 2週間の研修後、筆記試験・面接試験を受ける
- 審査により合格者が決定
詳しくは下記の表にまとめました。
| 公募期間 | 5月上旬から6月中旬 |
| 第1次審査(選抜試験) | 7月下旬の日曜日 |
| 合格発表 | 8月末頃、ホームページにて発表、合格者に通知 |
| 第2次審査(研修、面接、資格審査) | 第1期・9月後半から16日間・10月前半から6日間 第2期・10月前半から16日間・10月中旬から6日間 |
| 合格通知 | 11月下旬 |
試験会場と料金
【第1次試験】
| 会場 | 北海道、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡 |
| 料金 | 樹木医補の認定を受けていない:18,000円樹木医補の認定を受けている :15,000円 |
【第2次試験】
| 会場 | 動画講義 :Web配信実習及び研修:茨城県つくば市 |
| 料金 | 115,000円 |
その他、往復の交通費、宿泊費等を自分で用意しておく必要があります。また、研修講義では、公式テキスト「最新 樹木医の手引(8,500円)」を用意しましょう。
樹木医試験の内容
【1次試験】
一般教養、樹木に関する専門分野、高卒程度の生物の知識などの分野から出題されます。
- 択一式問題35問(90分)
- 論述式問題3問(90分)
【2次試験】
研修にて16科目を学びます。事前に公式テキストの「最新 樹木医の手引き」を学習しておく必要があります。
最後に筆記試験、適性試験が行われます。
樹木医の勉強方法と勉強期間
樹木医になるためにはどんな勉強をして、どれくらいの勉強期間が必要なのでしょうか。
ここで詳しくお伝えするので、受験勉強の参考にしてみてください。
過去問や参考書を読む
まずは日本緑化センター発行の「最新・樹木医の手引き(改訂4版)」を購入してください。樹木医研修の際にも、参考資料として使用されるので購入は必須であり、試験前に十分に読み込むことで試験対策にもなります。
過去問は「樹木医研修受講者選抜試験問題集」を読みましょう。
過去問を解くのは試験勉強の基本中の基本。過去問の解説を読んで内容を理解しておきましょう。
グリーンエージオンラインアカデミー(GOA)発行の「課題に答える文章の書き方1」では、論述式問題の解説をしているので、こちらも読んでおきましょう。
必要な勉強時間
樹木医になるための基本的な知識の習得は、普段からの継続的な勉強が必要になります。
樹木医補から樹木医というステップが王道であり時間がかかることや、試験の難易度が高いからです。
択一式問題や論述式問題の対策は、最低でも6ヶ月の期間を取るようにしてください。働きながら試験対策をするのは簡単ではないですが、通勤時間や休憩時間なども勉強に当てると合格率が上がるでしょう。
とはいえ、人によって生活サイクルが異なるので、試験日から逆算してどれくらの時間を避けるのかを考えてみてください。
樹木医の職業と年収
「樹木医は具体的にどんな職業に就けるの?年収はどれくらい?」
樹木医の職業と年収は様々なので、詳しく解説していきます。
樹木医の就職先
樹木医の主な就職先は下記のとおりです。
- 造園会社
- 林業会社
- 地方公共団体の農林・緑化関係職員
- 環境コンサルタント
樹木医は造園業界で特に需要が高く、樹木の健康管理や病気予防の業務を行います。林業会社では森林の管理や木材の生産に従事し、樹木の育成や保護に貢献します。
さらに、公的機関では役所や地方自治体の緑化担当課で働き、公共の樹木の管理や保護に関与することもあります。
専門業者においては、樹木医としての専門知識を生かし、樹木に関する調査やコンサルティングを行う企業で働くことも可能。樹木医を中心としたトータルサービスを提供する企業にも就職できます。
樹木医の年収
樹木医の年収は、所属する企業や団体、地域によって異なります。
例えば、厚生労働省 jobtagによると、樹木医と関連の深い造園業の平均年収は「約374.4万円」となっています。
環境コンサルタント会社の年収は「400万から600万円」と予想されています。
また、大学教員の樹木医や教授になると年収が高くなる傾向にあるようです。
まとめ:仕事内容と勉強方法を理解して樹木医を目指そう
樹木医は、樹木の健康を守り、緑豊かな環境づくりに貢献する重要な職業です。樹木医になるには、実務経験を積み重ね専門的な知識を深める必要があります。
試験は難易度が高く合格率も低めですが、しっかりとした準備と継続的な学習を行うことで、十分に合格できます。
職場環境として、造園会社や林業会社、公共機関、環境コンサルタントなど、多岐にわたる分野で活躍の場があり、努力次第で高い収入を得ることも可能です。
樹木医を目指すなら長期的な計画を立てることが大切。この記事を参考に、樹木医への道を切り開いてください。
なお、求人サイト「GARDEN-JOB」では、造園・外構・土木の求人を多数掲載中です。入社が決まると祝い金として最大5万円がもらえますので、ぜひGARDEN-JOBに登録して、樹木医のキャリアにお役立てください。
樹木医の知識と経験を活かして、樹木の保全・診断に関わる仕事を探そう!