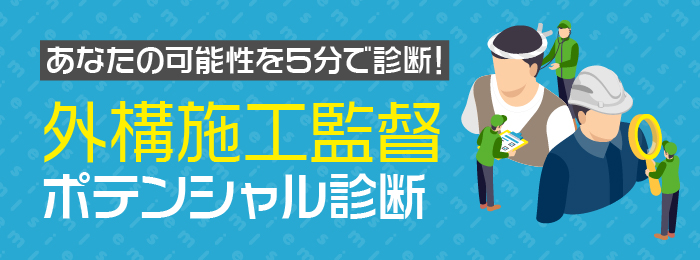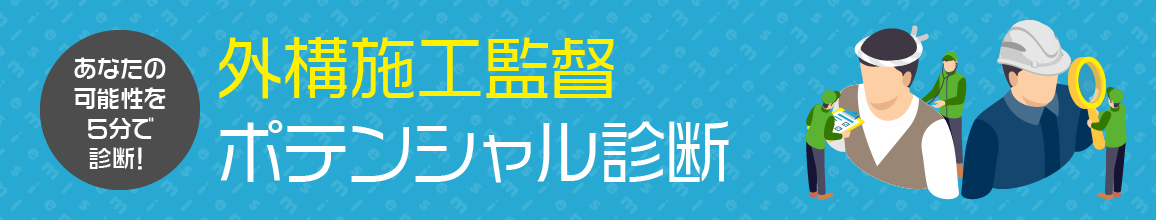「職方ってなんだろう?」
「職人との違いって何?」
「どうすれば職方になれるの?」
こんな疑問にお答えする記事です。
建設現場や工場で働く人を指す言葉ですが、「職人」との違いがよくわからないという方も多いでしょう。
この記事では、職方の意味や定義、職人との違い、そして職方になるための条件や仕事内容について詳しく解説します。
建設業や製造業に興味がある方、キャリアアップを考えている方にとって参考になる情報をお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。
 目次
目次
職方とは?

職方とは、建設業や製造業などで特定の職務や役割に従事する熟練工を指します。
ここでは、職方の定義と職人との違い、使用される場面の違いを解説します。
職方の定義
職方は主に現場での作業や指揮を担当します。
その専門分野における高度な技能を持ち、現場全体の作業の質と効率を高める重要な存在です。
長年の経験を通じて培った知識と技術を活かし、複雑な作業の遂行や問題解決に当たります。
また、若手作業員の育成や技術の伝承においても重要な役割を果たします。
職方と職人の違い
職方と職人の違いは下記のとおり。
| 職方 | 現場をまとめる立場にあることが多い |
| 現場全体を統括する | |
| 特定の職務や役割に従事する | |
| チーム全体をまとめる役目も担う | |
| 職人 | 特定の技術や工芸に特化した個人を指す |
| 特定の技術や知識を持つ人 | |
| 個々に腕を磨く | |
| ものづくりの専門家 |
職方は個人の技能だけでなく、組織の中での役割や責任が重要視される点で職人とは異なります。
自身の技能を発揮するだけでなく、他の作業員を指導し作業全体の進行を管理する役割を担います。
現場での意思決定者として、作業の効率化や品質管理、安全管理などの責任を負います。
ちなみに下記の記事では職人の種類ついて解説しています。こちらも合わせて読むと理解が深まりますのでどうぞ。
使用される場面の違い
職人と職方という言葉が使用される場面にも違いがあります。
職人は個々の技術を評価する際に使われることが多く、例えば「熟練の職人による手作り」といった表現で、その技術の高さや独自性を強調する際に用いられます。
一方、職方は組織内での位置づけを示す際に用いられることが多く、「大工職方」「左官職方」といった形で、その人物が現場でのリーダー的立場にあることを示します。
職人という言葉は、伝統工芸や専門的な技術を持つ個人を指す際に広く使用されますが、職方は主に建設業や製造業などの現場で使われる言葉です。
職方の種類と特徴
建設業では、様々な専門分野に応じた職方が存在します。
代表的なものとして、大工職方、左官職方、電気工事職方などがあります。
単に作業を行うだけでなく、その分野における作業計画の立案、品質管理、安全管理、そして部下の指導育成まで幅広い責任を負います。
現場での実務経験と専門知識を組み合わせ、工事現場全体の成功に大きく貢献しています。
職方の仕事内容と責任とは?

具体的な職方の仕事内容は下記のとおり。
- 現場の指揮
- 品質管理
- 安全管理
- コスト管理
1つずつ解説します。
現場の指揮
職方は現場でのリーダーシップを発揮し、作業の全体的な管理を担います。
具体的には、作業の進捗状況を把握し、適切な指示を出すことで作業の円滑な進行を確保します。
作業者間の連携を促進し、効率的な作業環境を整えることも職方の重要な責務です。
日々の作業計画を立て、各作業員に適切な任務を割り当てます。
作業員が困らないように、作業の優先順位を決定し、人員と資材・機材の適切な配置を指示しなければなりません。
品質管理
作業の品質を保つことは職方の重要な役割です。
職方は自身の専門知識と経験を活かし、作業の各段階で品質チェックを行います。
問題点を早期に発見し、必要な修正や改善を指示することで、最終的な成果物の品質を担保します。
品質管理においては、技術的な側面だけでなく、法令や規格への適合性も確認する必要があります。
また、品質管理の記録を適切に保管し、必要に応じて報告書を作成します。
安全管理
建設現場において、安全確保は最も重要な仕事の1つです。
安全規則の徹底、危険箇所の特定と対策、適切な保護具の使用指導などを通じて、作業員の安全を確保します。
例えば、作業開始前のミーティングで安全確認を行い注意を促したり、現場を巡回し危険な状況や不安全な行動がないかを確認します。
問題を発見した場合は、即座に作業を中止し、安全が確保されるまで再開できないように指示します。
作業員の健康管理にも気を配り、過度の疲労や体調不良による事故を防止するための対策を講じることも役割の1つです。
コスト管理
職方はコスト管理にも責任を負います。
限られた予算と時間内で工事を完遂するために、資材の適切な使用、作業手順の最適化、無駄の削減などに取り組みます。
必要な資材を過不足なく準備し、無駄な在庫を抱えないよう調整。作業の進捗に応じて適切なタイミングで資材を調達します。
また、新しい工具や機械の導入を提案し、作業の効率化と品質向上の両立を図ります。
職方になるためには?

それでは、職方になるためにはどうすればいいのでしょうか。
ここでは職方に必要な能力や経験、資格を見ていきましょう。
必要な技能と経験
職方になるためには、高度な技術的スキルと豊富な現場経験が不可欠です。
まず、その職種における基本的な技能を完全に習得することが求められます。
例えば、大工職方になるためには、木材加工技術、建築図面の読解能力、各種工具の使用技術などを身につける必要があります。
通常、見習いとして現場で働きながら徐々に習得していくのが一般的。技術的スキルに加えて、現場での実務経験も重要です。
職方になるまでには10年以上の経験が必要とされます。この期間中、様々な種類の工事に携わり、異なる条件下での作業方法や問題解決能力を身につけていきます。
また、現場でのコミュニケーション能力や、チームワークの重要性も学びます。
現場での経験を積みながら、徐々に責任ある立場を任されることで身につけていきます。
資格と認定
職方として認められるためには、特定の資格を取得することが求められます。
建設業では、例えば以下のような資格が重要視されます。
- 技能士
- 施工管理技士
- 技術士
- 安全衛生責任者
資格を取得することで、技術的な能力が公的に認められるだけでなく、より責任ある立場での仕事を任されやすくなります。
信頼の担保、技能向上の証明にもなるため、キャリアアップにも有利になります。
職方を目指す上では、現場経験とともに資格取得を計画的に進めていくことが重要です。
職方のやりがい

職方の仕事には多くのやりがいや魅力があります。
ここでは下記3つを取り上げますのでご覧ください。
- 工事完遂の達成感
- 社会インフラ整備への貢献
- 技術の追求
工事完遂の達成感
大規模工事の完成に携わることで得られる充実感・達成感は職方の仕事の大きな魅力の一つです。
例えば、高層ビルの建設や大規模な橋梁工事など、何ヶ月、時には何年もかけて取り組んできた工事が完成した時の喜びは格別です。
自分たちの手で街の景観を変え、新しい価値を創造したという実感は、他の職業では味わえない特別なものと言えるでしょう。
また、工事の各段階で直面する様々な課題を一つ一つ克服していく過程も、大きな達成感をもたらします。
予期せぬ問題が発生しても、チームで知恵を絞り、創意工夫を重ねて解決策を見出すことは、職方としての能力と経験を最大限に活かす機会となります。
完成した建造物が長年にわたって使用され、多くの人々の生活や仕事の場となることを想像すると、自分の仕事が社会に長期的な影響を与えるという実感が得られます。
社会インフラ整備への貢献
職方の仕事は、社会基盤の整備や維持に直接的に貢献できる点で大きなやりがいがあります。
道路、橋、ダム、鉄道、空港など、私たちの日常生活や経済活動を支える重要なインフラの建設や維持管理に携わることができます。
地域や国の発展に直接的に寄与するものばかりなので、社会的意義が非常に高いと言えます。
例えば、新しい道路や橋の建設に携わることで、人々の移動をより便利にし、地域間の交流を促進することができます。
災害に強い建造物を作ることで、人々の安全を守ることにも貢献できます。
このように、自分の仕事が社会の発展や安全に直接的に繋がっているという実感は、大きなやりがいとなるでしょう。
技術の追求
技術向上の過程自体が喜びになり、日々の仕事を通じて自己成長を実感できることが、職方の大きなやりがいの一つです。
例えば、左官職方の場合、壁の仕上げ一つとっても、その技術を極めるには何年もの経験と研鑽が必要です。
しかし、その努力の末に生み出される美しい仕上がりは、まさに芸術作品と呼べるものです。
高度な技術を追求し磨き上げていく過程は、職方にとって大きな喜びとなります。
また、環境に配慮した新素材の使用方法を習得したり、最新のデジタル技術を活用した施工管理を学んだりすることで、自身の技術の幅を広げることもできます。
職方は、自身の技術を若手に伝承していくことも重要な役割。
長年培ってきた技術や知恵を次世代に引き継ぐことで、建設業界全体の技術水準の向上に貢献できることも大きなやりがいになります。
職方のキャリア展望

職人から職方となったあとは、どのようなキャリアが考えられるのでしょうか。
詳しく解説します。
更にキャリアアップできる可能性はある?
さらに多くの経験を積むにつれて、より大きな責任を担う立場へキャリアアップできる可能性があります。
まず、現場監督への昇進が考えられます。現場監督は、複数の職方をまとめ、工事全体の進行を管理する立場です。
次に、工事主任や工事長への昇進も可能性があります。より大規模な工事の責任者として、複数の現場を統括したり、発注者との交渉を行ったりする役割を担います。
技術部門の管理職への道も考えられます。例えば、技術部長や工事部長といった役職では、会社全体の技術戦略の立案や、大規模プロジェクトの統括などを行います。
ただし、昇進の可能性は、個人の能力や実績、会社の規模や方針によって異なります。
独立開業の選択肢はある?
職方の経験を活かして独立開業する選択肢も十分に考えられます。
ただし、独立には様々な課題もあるため、慎重に検討する必要があります。
独立を考える際は、十分な技術力と経験を持っていることはもちろん、経営に関する知識や人脈も重要。
また、独立前に経営や財務に関する勉強をしたり、同業者のネットワークを構築したりしなければなりません。
まずは個人事業主として小規模な仕事から始め、徐々に事業を拡大していくのが一般的です。
独立開業は、職方としての経験を最大限に活かせる選択肢の一つですが、慎重な計画と準備が必要です。
独立する際は、自身の技術力や経営能力、市場の状況などを十分に見極めた上で判断するようにしましょう。
ちなみに下記の記事では独立した場合の年収を解説しています。興味のある方はぜひご覧ください。
まとめ:職方は現場での作業や指揮を担当する熟練された職人

職方は、建設業や製造業において現場の要となる熟練技能者です。
高度な技術と豊富な経験を持ち、作業の指揮や品質管理、安全管理などの重要な役割を担います。
職人との違いは、より広範な責任と管理能力が求められる点にあります。
これから職方を目指す方は、まずは職人から初めてみましょう。職人からのキャリアアップを考えている方は、大きな建設会社へ転職することも検討すると良いでしょう。
なお、職人や職方のお仕事をお探しの方は、GARDEN-JOBへの登録をおすすめします。
GARDEN-JOBは、造園・園芸・外構・土木職人専門の転職求人サイトで、関西、東海、関東エリアの求人情報を掲載しています。
採用お祝い金最大5万円の特典もあり、造園職人や庭師、外構職人、左官職人、金物系職人など、庭に関する工事の職人さんと、現場を監督していく施工管理技師など、造園・外構業界専門の求人情報を提供しています。
会員登録をすると、企業とのメッセージのやりとりや応募履歴の確認など便利な機能がご利用いただけます。
職人、職方としてのキャリアを考えている方は、ぜひGARDEN-JOBを活用してみてください。