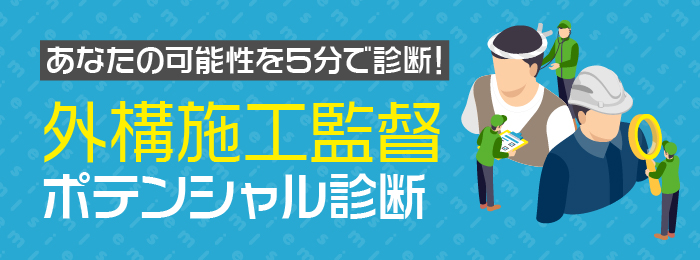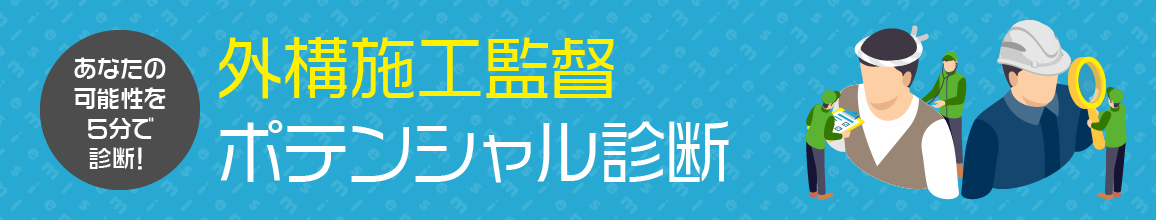「施工監督の仕事内容を知りたい」
「施工監督になるにはどうすればいいの?」
そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
施工監督は建設現場全体を統括する重要な役割を担い、高度な専門知識とスキルが求められる職業です。
本記事では、施工監督の具体的な仕事内容から、必要なスキル、なるまでのステップ、年収まで詳しく解説します。
施工監督を目指す方や建設業界に興味がある方にとって、有益な情報が満載ですのでぜひ最後までご覧ください。
 目次
目次
施工管理とは

施工管理は、建設現場の様々な管理を行うことです。
主に工程管理、安全管理、品質管理の3つの管理が中心となります。
この3つの管理の具体的な仕事内容は下記のとおり。
| 管理項目 | 具体的な仕事内容 |
|---|---|
| 工程管理 | ・工事スケジュールの作成 ・進捗状況の確認 ・遅れの調整・資材や人員の手配 |
| 安全管理 | ・安全設備(手すりなど)の設置 ・朝礼での安全指導 ・定期的な現場パトロール ・作業員の健康チェック |
| 品質管理 | ・材料や寸法のチェック ・施工状況の確認 ・定期的な品質検査 ・問題箇所の修正指示 |
施工管理の業務は多岐にわたり、現場での作業だけでなく、事務作業や関係者との調整など幅広い仕事があります。
施工監督の仕事内容

施工監督の仕事内容は下記のとおり。
- 事前準備と計画立案
- 現場管理
- 調整・問題解決
- 完工・引き渡し
順番に解説します。
1. 事前準備・計画立案
事前準備と計画立案は、工事の基礎となる重要な段階です。
事前準備と計画立案は、具体的に下記の順序で行われます。
| 段階 | 具体的な内容 | 重要ポイント |
|---|---|---|
| 1. 設計図の確認と工事概要の把握 | • 建築家や設計者の図面を詳細に確認 • 工事の全体像を理解 • 疑問点を設計者に確認 • 施工上の問題点を洗い出し | • 細部まで注意深く確認 • 設計者とのコミュニケーション |
| 2. 施工計画の策定 | • 工法の決定 • 必要な資材の把握と調達計画の立案 • 人員の配置計画の作成 | • 効率性と安全性の両立 • 綿密な計画立案 |
| 3. 工程表の作成 | • 各作業の所要時間の見積もり • 作業の順序と依存関係の整理 • 資材の調達タイミングの計画 • 不確定要素への対応策の検討 | • 詳細なスケジュール管理 • 柔軟性の確保 |
| 4. 安全対策の立案 | • 作業員の安全確保策の検討 • 事故防止のための具体的対策の立案 | • 労働安全衛生法の遵守 • リスクアセスメント |
| 5. 行政への申請書類作成 | • 建築基準法や消防法に沿った書類の作成 • 必要な許認可の確認と申請 | • 法令遵守の徹底 • 正確な書類作成 |
施工監督は、設計者や主任技術者、発注者などと、事前準備と計画立案を適切に実施し、工事がスムーズに進行できるようにしていきます。
2. 現場管理
現場管理は施工監督の中心的な業務であり、日々の工事を滞りなく進めるために不可欠です。
具体的には下記の作業(QCDSE)を行います。
| 管理名 | 主な管理ポイント |
|---|---|
| Quality(品質) | ・図面通りの工事確認 ・法規に則った強度・耐震基準のクリア ・工事手順書の作成 ・資材の写真撮影 |
| Cost(原価) | ・無駄のない資材在庫管理 ・人員配置の最適化 ・予算内での工事進行確認 |
| Delivery(工期) | ・工程表の調整 ・進捗状況の確認 ・工期短縮の周知 |
| Safety(安全) | ・危険個所の抽出 ・安全対策の立案 ・作業員への安全教育 |
| Environment(環境) | ・周辺環境への騒音・振動対策 ・職場環境の整備 |
最も優先するのは「安全管理」です。
安全が確保されていないと、事故が発生し後期や品質に影響を与えるからです。
例えば、事故が起これば、工事の中断や中止を余儀なくされます。
万が一、死傷事故が起きれば、依頼主や周辺の方や利用者に良い印象を持たれません。
したがって、QCDSEの中で、安全管理を最優先に考え、作業員の安全確保と事故防止に努めることが、現場管理において最も重要なポイントとなります。
ちなみに下記の記事でもQCDSEについて詳しく解説しています。QCDSEは施工監督に必須の知識なので、ぜひ合わせてご覧ください。
3. 調整と問題解決
建設現場では様々な問題が発生します。
施工監督は様々な問題を迅速に解決し、工事を円滑に進めなければなりません。
そのため、工事の品質を確保するために、定期的な品質検査と調整を行います。
具体的には、施主の希望する規格基準を確認し、計画通りに施工がされているかチェックします。
不具合を発見した場合はすぐに修正指示を出し、問題の原因を特定。再発防止策を講じます。
また、職人や関連業者と密にコミュニケーションを取ることで、トラブルを未然に防ぎます。
問題が起きた場合、設計変更や工程の調整を行い、安全、品質、工期の確保に努めます。
4. 引き渡し
施工監督が行う引き渡しとは、完成した建物を施主や依頼主に渡すことを指します。
施工監督は引き渡しで以下の作業を行います。
【最終検査】
建物の品質や安全性を最終確認します。細部まで丁寧にチェックし、問題がないことを確認します。
問題が合った場合は対応策を立案します。
【建物の説明と使用方法の指導】
施主や依頼主に、完成した建物の特徴や注意点を分かりやすく説明し、適切な使用方法を指導します。
【必要書類の作成と提出】
完工証明書や保証書など様々な書類を作成し、関係各所に提出します。
以上を行い引き渡しの終了です。
また、引き渡し後も、アフターケアの一環として施主からの問い合わせや不具合の対応を行うことがあります。
施工監督に必要なスキル
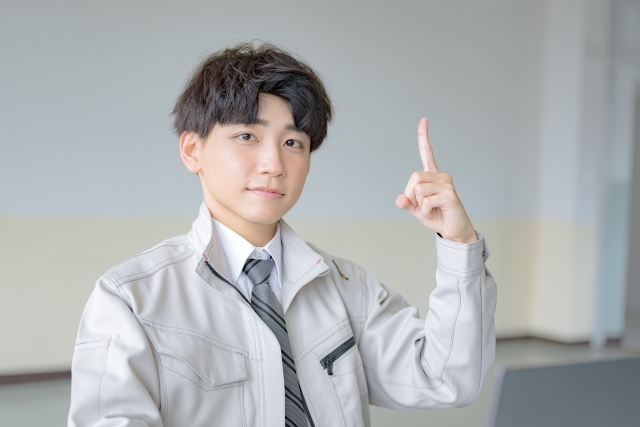
施工監督の仕事を適切に行うには、多岐にわたるスキルが必要不可欠です。
施工現場では様々な問題に直面するため、複数のスキルを組み合わせて対応しなければならないからです。
具体的には下記のスキルが必要。
- コミュニケーション能力や交渉力
- リーダーシップ
- マルチタスクスキル
- 問題解決スキル
- 責任感と強い精神力
詳しく見ていきます。
コミュニケーションスキルや交渉力
施工監督は、コミュニケーションスキルと交渉力がとても大切です。
工事現場では、多くの業者や職人と連携して仕事を進める必要があるからです。
施工監督は、現場でのコミュニケーションの中心となる役割を果たします。職人や業者と話し合いながら、工事のの目標・目的を共有し、問題を早めに解決することが求められます。
関係者と良い関係を築くには、ただ情報を伝えるだけでなく、相手の気持ちや意見も理解することが大切です。
また、予算や工期などの制約の中で最良の結果を出すために、交渉力が必要です。例えば、工事の進行に影響を与える問題が発生した場合、その解決策について関係者と話し合う必要があります。
コミュニケーションスキルは、普段から人と話すことを意識したり、会話や交渉力について解説した書籍を読むことで向上できるでしょう。
リーダーシップ
施工監督には高いリーダーシップが不可欠です。
施工監督は現場全体を指揮し、多くの職人を統括する立場にあるため、リーダーシップなしでは円滑な工事進行が困難になります。
現場では予期せぬ問題が発生することも多く、そのような状況下で冷静に判断し、適切な指示を出せるかどうかが問われます。
結果として、高いリーダーシップを持つ施工監督は、工事の成功率を高め、職人からの信頼も厚くなります。
また、リーダーシップは生まれつきの才能ではなく、努力によって磨くことができるスキルです。
日々の業務の中で意識的にリーダーシップを実践し、その結果を振り返ることで徐々に向上できるでしょう。
マルチタスクスキル
マルチタスクスキルは、複数の業務を効率的に進めるための技能です。
施工管理は現場の巡回や電話対応、書類作成や打ち合わせなど、複数の業務を同時に進めるケースが多いです。
下記のように仕事を行うことで業務効率が向上します。
- 業務ごとに優先順位をつける
- 状況に応じて作業を切り替える
- タスクにかかる時間を把握する
- すべての業務をバランスよくこなす
しかし、マルチタスクは注意力を分散させ、生産性を低下させる可能性もあるため、計画(Plan)、実施(Do)、検討(Check)、改善(Act)の、PDCAサイクルを回しながら、マルチタスクの効率を向上させることが大切。
PDCAサイクルとは、業務や学習の効率を向上させるフレームワークのこと。
具体的には、目標を立て、それに向けた行動を起こし、結果を振り返り、改善策を取り入れるというプロセスです。
PDCAサイクルを簡潔に解説すると下記のようになります。
| ステップ | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| Plan(計画) | 目標を決め、達成に向けた具体的な計画を立てる。 現状を分析し、問題点を見つけて解決策を考える。 | 業務の方向性を明確にし、効率的に進めるための準備をする。 |
| Do(実行) | 計画に基づいて実際に行動を起こす。 計画通りに進めることが重要。 | 計画した内容を現場で実行し、目標達成に向けて進む。 |
| Check(評価) | 実行した結果を確認し、計画と実績を比較して問題点やズレを見つける。 データや数値で評価することが効果的。 | 実行の成果を測定し、改善点や課題を明確にする。 |
| Action(改善) | 評価で見つけた問題に基づいて改善策を考え、次回の計画に反映させる。 | 業務の質や効率を向上させるための改善を行う。 |
それぞれの段階が連携して業務改善につながります。
マルチタスクが苦手な方は、まずPDCAサイクルを意識してみると良いでしょう。
問題解決スキル
問題解決スキルも施工監督に必須です。
工事現場では、以下のようなトラブルが起きる可能性があるからです。
- 作業中の事故や不注意による怪我が発生する
- 業者間で意見の相違がありトラブルになる
- 資材が届かないため工事ができない
- 建設機械の故障により作業が中断される
- 急な欠員や労働力不足で工事が進まない
- 雨や強風などの悪天候が続き工事が遅れる
問題が起きないように注意していても、どうしてもトラブルは発生します。工事現場ではトラブルが無いことのほうが少ないと考えてよいでしょう。
そのため、トラブルが発生した際に、迅速かつ柔軟に対応する能力が求められます。
責任感と強い精神力
施工監督は、職人と発注者の間に立つ立場であるため、双方の意見や要求を調整する役割を担います。
ストレスがかかる場面が多く、最後まで仕事をやり遂げる責任感と、それを支える強い精神力が求められます。
例えば、職人からは「作業環境をもっと良くしてほしい」などの要望が出される一方で、発注者からは「工期を短縮してほしい」などの厳しい要求が寄せられることがあります。
このような板挟みの状況でも、冷静に対応し、最善の解決策を見つける力が必要になります。
施工監督に向いてる人とは?

施工監督は責任が大きく多岐に渡る業務があるため、様々なスキルを持つ人じゃないと務まりません。
先ほどご紹介した施工監督に必要なスキルを踏まえると、下記に当てはまる人が向いてると言えます。
【施工監督に向いてる人】
- コミュニケーション能力高い
- 決断力がある
- 達成意識が高い
- 原因分析ができる
- 高い目標を持てる
- マルチタスクが得意
- 責任感がある
- 他責にしない
- 柔軟性がある
- スケジュール管理ができる
- 整理整頓ができる
- 協力して作業できる
- 仕事が丁寧
- ストレス耐性が高い
- 切り替えが早い
苦手なことは学習や現場経験を積んで克服していけばいいので、全部当てはまる必要はありません。
もしあなたが向いてそうなら、施工監督になる方法を学んでいきましょう。
施工監督になるまでのステップ
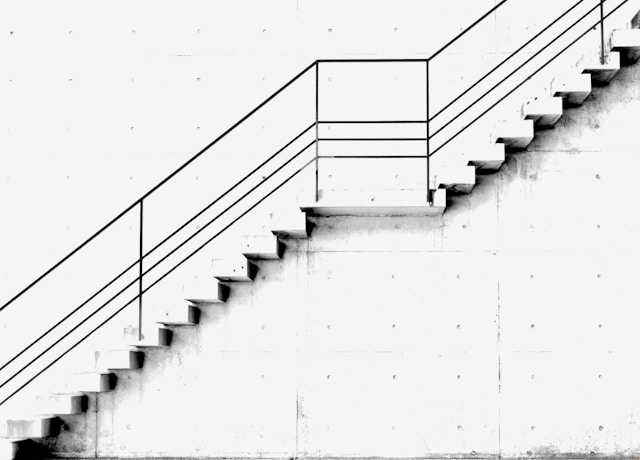
「どうすれば施工監督になれるのかな?」
施工監督になるには、高い専門知識と様々なスキルが必要です。
そのため、すぐに施工監督にはなれません。
ここで施工監督になるまでの1例をお伝えするので、参考にしてみてください。
専門学校に通う
施工監督を目指すために、建築や施工管理を専門的に学べる専門学校に進学します。建築に関する基礎知識から実務スキルまでを段階的に学ぶことができます。
例えば、「建築監督科」や「現場監督育成コース」など、施工管理職に特化した授業がある学校を選ぶと良いでしょう。
多くの専門学校では、インターンシップ制度を導入しており、実際の工事現場でプロから直接指導を受ける機会もあります。
施工管理の実務経験を積む
施工管理アシスタントとして現場に入り、基本的な業務を学びます。
【主な就職先】
- ゼネコン
- ハウスメーカー
- 建設設計事務所
- 建設コンサルタントなど
アシスタントの時点では、申請書類の作成や現場写真の撮影、簡単な工程管理などを担当し、施工管理の基礎知識を身につけます。
2施工管理技士を取得
次に目指すべきは「2級施工管理技士」の資格取得です。
資格取得により、施工管理技士としての技能が公式に証明され、小規模な工事現場を任されるようになります。
2級施工管理技士として働きながら、工程管理や品質管理、安全管理などのスキルを深めます。この間にリーダーシップや問題解決能力も磨かれます。
また、この期間中に原価管理やコスト意識も身につけることが重要です。
1級施工管理技士を取得
一定期間の実務経験を積み、「1級施工管理技士」の受験資格を目指します。
1旧施工管理技士は、大規模工事や複雑な工事の管理を行うために必要不可欠であり、キャリアアップには欠かせません。
1級取得後は、大手建設会社での活躍や監理技術者として現場全体を統括する立場に進めるようになります。
施工監督として独り立ち
1級施工管理技士などの上位資格を取得した後は、施工監督として工事全体を統括する立場になります。
これまでの知識や経験を活かし、職人への指示出しや工程調整、安全確認など、多岐にわたる業務を担当します。
最終学歴にもよりますが、施工監督になるには、およそ5年〜15年かかると予想されます。
施工監督の必須資格
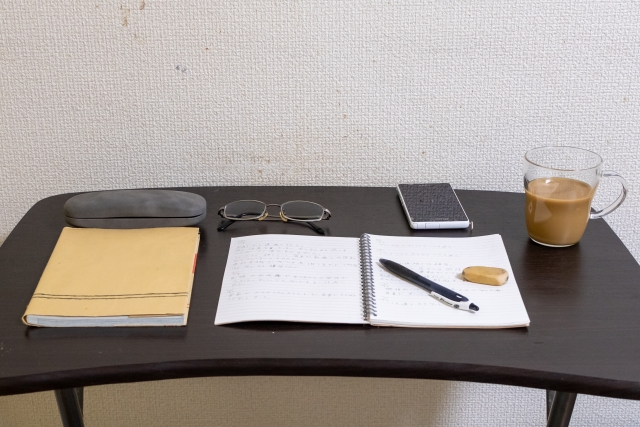
建設工事の管理を担当するためには、資格の取得が必須です。
ここでは、主な関連資格である施工管理技士と建築士をご紹介します。
施工管理技士
施工管理には、施工管理技士が必須です。
施工管理は資格が無くてもできますが、品質と安全、信頼の確保が必要だからです。
施工監督になる場合、1級が必須と言えるでしょう。
建築、土木、電気、管工事、造園、建設機械、電気通信工事の7つの分野があるため、工事内容、企業の専門性に合わせて取得するのが一般的です。
下記の記事では土木施工管理技士の資格を取得する方法をお伝えしています。受験資格や勉強方法が分かりますので、ぜひご覧ください。
建築士
建築士は、建物を設計したり工事を監督したりするための国家資格です。
建築士には「1級建築士」「2級建築士」「木造建築士」の3種類があり、それぞれ設計できる建物の規模や用途が異なります。
デザイン性だけでなく、安全性や環境への配慮も求められるため、幅広い知識とスキルが必要です。
具体的には、平面図や断面図の作成、設計意図を文章で説明するスキルなどが求められます。
2級土木施工管理技士の資格を活かして、実務経験を積める職場を探そう!
施工監督の年収

施工管理職である「土木施工管理技術者」の年収は、603.9万円です。
施工管理アシスタントと予想される20代のうちは300〜500万程度ですが、30代を超えた辺りから600万円を超え、40代後半になると650万円になります。
50代がピークで730万円ほどです。
施工監督になるのに最低5年〜15年かかることを考えると、施工監督の年収は600万円前後〜730万円ほどと予想されます。
しかし、経験や資格、専門性、企業規模により大きく変わることに注意してください。
大手ゼネコンでは年収が高く、スーパーゼネコンでは1,000万円を超えることもありますが、中小企業ではそれに比べて低い傾向があります。
参考資料:厚生労働省jobtag
まとめ:施工監督の仕事は責任が大きいが高い年収が魅力

施工管理は、工程管理、安全管理、品質管理を中心とした建設現場の総合的な管理業務です。
施工監督は、この管理業務を統括し、事前準備から完工・引き渡しまでの全工程を指揮する重要な役割を担います。
施工監督は、コミュニケーション能力、リーダーシップ、問題解決スキルなど多岐にわたる能力が求められます。
責任が大きいですが、やりがいのある仕事です。施工監督になるために、まずは一歩見出してみて下さい。
なお、造園・園芸・外構・土木職人専門の転職求人サイト「GARDEN-JOB」では、関西、東海、関東エリアの求人情報を掲載しております。
正社員・契約社員・アルバイトの造園職人や庭師、外構職人、左官職人、金物系職人、施工管理技師など、造園・外構業界専門の求人情報が豊富です。
会員登録で企業とのメッセージのやりとりや応募履歴の確認など便利な機能が利用できます。
GARDEN-JOBから就職が決まれば、最大5万円の祝い金もご用意していますので、ぜひこの機会にご登録ください。