「土木業界の現状や将来性を知りたい」
「人手不足や高齢化が深刻と聞くけど、実際どうなのかな?」
「国の政策や最新技術の影響も知りたい」
土木業界への就職を考える方は、こうした疑問を持つことが多いでしょう。
本記事では、土木業界の現状、課題、最新の政策、将来性について詳しく解説します。
 目次
目次
土木業界とは?

土木業界は、私たちの暮らしや経済の基盤を支える重要な分野です。
インフラの老朽化や自然災害への対応、そして新しい技術の導入など、さまざまな課題と向き合いながら、社会の安全・安心を守っています。
詳しく見ていきましょう。
土木業界の役割と重要性
土木業界は、道路や橋、トンネル、ダム、河川、港湾などの社会インフラを建設・維持管理する分野です。
インフラは、生活や経済活動の基盤であり、災害時の復旧・復興にも不可欠です。
国土強靭化や防災・減災の観点からも、土木業界の役割は今後ますます重要視されています。
近年では、自然災害の激甚化やインフラの老朽化への対応が急務となっており、国や自治体も積極的な投資と政策支援を行っています。
主な土木工事の種類
主な土木工事は下記のとおり。
| 工事名 | 主な内容・特徴 |
|---|---|
| 道路工事 | 道路の新設・拡幅・改良、舗装や橋・トンネルの付帯施設を含む整備工事 |
| 橋梁工事 | 川や海・道路等に橋を架ける工事。橋台、橋脚、橋桁などの施工が含まれる |
| トンネル工事 | 山岳部や市街地地下などにトンネルを掘削し、道路・鉄道・上下水道などを通す工事 |
| ダム工事 | 洪水防止や水資源確保、発電などを目的にダムを建設する工事 |
| 河川工事 | 河川の護岸・掘削・堤防・水門などを設置し、水害防止や水路の安定化を図る工事 |
| 港湾工事 | 港や岸壁、埠頭、護岸、荷役施設、航路などを整備する工事 |
| 上下水道工事 | 上水道・下水道の本管・取付管・ポンプ場・処理場などの設置・更新工事 |
| 造成工事 | 宅地や工業団地、公園などを新たに造成し、土地を利用しやすく整備する工事 |
各分野は専門性が高く、設計から施工、維持管理まで多様な技術と知識が求められます。
都市部と地方で必要とされる工事の種類や規模も異なり、都市部では再開発や大規模インフラの更新、地方ではインフラ維持や防災工事が中心です。
土木業界の現状

土木業界は、私たちの生活や経済を支えるインフラを造り続けています。
最近は市場規模が拡大する一方で、資材や人件費の高騰、人手不足、インフラの老朽化など、さまざまな課題も出てきています。
都市部と地方で状況が異なるのも特徴です。
市場規模と成長性
2023年度の国内建設8大市場の市場規模は「24兆2,989億円」(前年度比104.8%)と拡大傾向にあります。
(出典:日本経済新聞)
新型コロナウイルス禍で延期されていた工事の再開や、物流倉庫・工場の建設需要が市場拡大を後押ししています。
一方で、資材価格や労務費の高騰が経営に影響を与えており、労務費高騰の背景には人手不足があると指摘されています。
今後もインフラ整備や防災需要が堅調なため、安定した需要が見込まれています。
インフラ老朽化と更新需要
日本のインフラは高度経済成長期に整備されたものが多く、老朽化が深刻な課題です。
橋梁やトンネルなどは耐用年数を超えるものが増えており、補修・更新工事の需要が全国で高まっています。
国や自治体は計画的な点検・修繕を進めており、今後も安定した市場規模が維持される見通しです。
地方と都市部の違い
土木工事の需要や内容は、都市部と地方で大きく異なります。
都市部では再開発や大規模インフラの更新が進む一方、地方では人口減少や財政難による新規投資の抑制が課題です。
地方ではインフラ維持管理の負担が重く、効率的な運用が求められています。
地方の中小企業では人手不足が特に深刻で、仕事を受注できず経営難に陥るケースも増えています。
インフラ整備の遅れが及ぼす影響
インフラ整備や更新が遅れると、災害時のリスク増大や経済活動の停滞につながります。
例えば、老朽化した橋や道路の事故リスク、交通インフラの機能低下、物流網の寸断などが現実的な問題です。
国や自治体は限られた予算と人材の中で、優先順位をつけて整備を進めています。
土木業界の課題

土木業界は今、大きな課題に直面しています。
人手不足や高齢化が進み、団塊世代の大量退職によって現場の担い手が急激に減っています。
若い人が少なく、ベテランの技術や経験を次世代に伝えるのも難しくなっています。
また、長時間労働や休日の少なさといった働き方の問題もあり、労働環境の改善が求められています。
それでは、こうした課題について詳しく見ていきましょう。
人手不足と高齢化の進行
2025年問題として、団塊世代の大量退職が進むことで、土木業界の人手不足は一層深刻化しています。
国土交通省のデータによると、建設業就業者数は1997年の685万人から、2023年には483万人へと約30%減少しています。
(出典:国土交通省「建設業を巡る現状と課題」)
2024年時点で、55歳以上が約37%、29歳以下は約12%と高齢化が著しく、若手人材の確保が大きな課題です。
今後10年で約80万人の60歳以上技能者が引退する見込みで、2025年以降は約90万人の職人が不足すると予測されています。
(出典:日本建設業連合会「建設業の現状」)
技術継承の難しさ
高齢化が進む中で、熟練技術者の引退による技術継承が大きな課題です。
OJTや研修制度の充実、ICT技術の活用による効率化が進められていますが、現場ごとに異なる知見の伝承には時間と労力がかかります。
厚生労働省も技術継承のための人材育成や研修支援に力を入れています。
働き方改革と労働環境の改善
長時間労働や休日の少なさが人材確保の壁となっています。
厚生労働省の「毎月勤労統計調査(令和6年2月分結果速報)」によると、建設業の1か月平均総実労働時間は163.5時間で、他産業に比べて長い傾向があります。
2024年4月からは時間外労働に罰則付きの上限が設けられ、働き方改革関連法が施行されています。
政府は週休2日制の導入や労働時間短縮を推進し、現場の生産性向上や安全対策の強化も進めています。
(出典:厚生労働省「建設業における時間外労働の上限規制について」)
廃業増加の背景と影響
中小建設業者の廃業が増加傾向にあります。
帝国データバンクの調査によると、2025年上半期の建設業倒産件数は前年同期比7.5%増の986件と、過去最多を記録しました。
主な要因は、人手不足や後継者不在、経営環境の悪化です。
廃業が進むことで、地域のインフラ維持や災害対応力の低下が懸念されています。
業界再編やM&Aも進み、持続可能な事業体制づくりが求められています。
(出典:帝国データバンク「建設業の倒産動向2025年度上半期」)
熱中症死傷者数の増加
近年、建設業における熱中症による死傷者数が急増しています。
厚生労働省の発表によれば、2024年の職場での熱中症による死傷者数(死亡・休業4日以上)は1,257人と、統計開始以来最多となりました。
そのうち建設業の死傷者は228人、死亡者は10人と全業種で最も多くなっています。
2020年以降の5年間でも、建設業は死傷者数・死亡者数ともにワースト1位の年が多く、特に高齢労働者の割合が高い現場ではリスクが顕著です。
死亡災害の多くは重篤化した状態で発見されるケースや、初期対応の遅れが要因となっています。
2025年6月からは熱中症対策の義務化が始まりました。
しかし、多数の事業者が混在する現場では実効性の確保が引き続き課題です。
人材確保・効率化の取り組み

人手不足により、一人当たりの業務負担が増加し、現場の安全性や品質管理に影響が出るケースが見られます。
作業効率の低下や事故リスクの増加が懸念されており、現場の安全管理体制の強化が急がれています。
女性や若手の活躍推進
厚生労働省は、若者や女性の建設業への入職や定着の促進に重点を置いています。
女性専用の更衣室やトイレの設置、育児と仕事の両立支援、キャリアアップ支援など、多様な人材が働きやすい職場環境づくりが進められています。
若手技術者の育成や業界の魅力発信も積極的に行われています。
ICT・DX導入による効率化
ICTやDXの導入が進み、現場の業務効率化や省人化が図られています。
具体的には、ドローン、3D測量、遠隔操作機械、建設機械の自動化など、最新技術の活用が進展しています。
生産性向上と人手不足対策の両立を目指し、業界全体でデジタル化が加速しています。
2025年6月義務化「建設業の熱中症対策」

2025年6月から、建設現場などの屋外作業で熱中症対策が法律で義務になりました。
守らないと罰金や罰則があるため、現場の安全を守るためにしっかり取り組むことが求められています。
それでは、具体的な内容や現場での課題について、詳しく見ていきましょう。
熱中症対策義務化の背景と内容
2025年6月1日から、厚生労働省は労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則を改正し、建設業を含む屋外作業現場での熱中症対策を事業者に義務付けました。
具体的には、熱中症の自覚症状がある作業者や、熱中症のおそれがある作業者を発見した場合の、報告体制の整備・周知、作業からの離脱や身体の冷却、必要に応じた医師の診察などが義務化されました。
WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下で、1時間以上または1日4時間を超える作業には必ず対策を講じる必要があります。
夏の建設業は、ほとんどの場合で対象となります。
違反した場合には、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
現場の課題と実効性
帝国データバンクの調査によれば、建設業界は今回の義務化に対する認知度が79.3%と高い一方、多数の事業者が混在する現場では「正しく履行できるか不安」という声も多く、実効性の確保が課題です。
熱中症対策の責任は各事業者にあり、現場任せや曖昧な指示ではなく、事業主が自ら体制を整え、指導・実行することが求められています。
(出典:帝国データバンク)
デジタル化の取り組み

土木業界では、国土交通省が中心となって「i-Construction」やDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進しています。
i-Constructionの推進
国土交通省は「i-Construction」を推進し、ICT技術を活用した建設現場の生産性向上を目指しています。
ドローンによる測量やICT建機の導入、BIM/CIMの活用など、現場の自動化・効率化が進められています。
i-Constructionは人手不足対策だけでなく、品質向上や安全性確保にも役立っています。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の導入
建設業界全体で、DXの導入が加速しています。
具体的には、業務のデジタル化やペーパーレス化、BIM/CIMの導入、クラウド型管理システムの活用など、現場とオフィスの連携強化が進められています。
データ活用による工程管理やコスト削減、遠隔監督なども実現しつつあります。
DX化のメリットは下記のとおり。
| メリット | 内容・効果 |
|---|---|
| 業務効率化と生産性向上 | 図面や測量データをデジタル化・一元管理し、現場と事務所での重複作業や無駄を削減。作業スピードや生産性が大幅に向上。 |
| 人手不足の解消・省人化 | 遠隔監督や重機の自動・遠隔操作、クラウド共有の活用で少人数でも業務遂行が可能になり、人手不足の現場でも効率よく運営できる。 |
| 長時間労働の是正・働き方改革推進 | タブレットやスマートフォンで現場からすぐに報告・承認可能に。移動や書類整理が不要になり、残業や移動負担を軽減。 |
| 技術継承・ノウハウ共有の円滑化 | BIM/CIM、現場映像、データを使った教育・指導がしやすくなり、技術やノウハウの標準化、若手や未経験者への技術伝承が効率的に行える。 |
| 安全性の向上 | ドローンやAIカメラで現場を遠隔監視、危険エリアの自動検知などで事故リスクを減少。ヒヤリハットや作業ミスの早期発見にも貢献。 |
| コスト削減 | ペーパーレス化、情報の一元管理、自動化による事務・労務コスト削減が実現。現場全体の経営効率がアップし、収益改善に役立つ。 |
国や自治体による支援策・補助金
国や自治体は、ICT・DX導入を支援する補助金や助成制度を設けています。
中小企業向けの設備投資支援や、技術研修の補助なども拡充されています。
法改正や規制緩和も進み、業界全体のデジタル化を後押ししています。
土木業界の将来性

土木業界の将来性はとても気になるのではないでしょうか。
ここでは土木業界の将来性を、国や自治体の施策と投資、新技術による変革、グローバル展開の可能性の3つに分けて解説します。
国や自治体の施策と投資
国土強靭化計画や防災・減災対策、インフラ長寿命化計画など、国や自治体は長期的な視点で土木分野への投資を継続しています。
公共投資は市場全体の約3分の1を占め、安定した需要を支えています。今後も持続的な投資が期待されます。
新技術の導入による変革
AIやロボティクス、IoTなど新技術の導入が進み、土木業界は大きな変革期を迎えています。
自動運転建設機械や遠隔操作技術、デジタルツインの活用など、現場の生産性や安全性が飛躍的に向上しています。
新技術の普及は、業界の魅力向上や人材確保にもつながっています。
グローバル展開の可能性
日本の土木技術は高い評価を受けており、海外インフラ市場への展開も進んでいます。
政府は2025年の海外インフラ受注額目標を34兆円と掲げ、アジアや中東、アフリカなどで日本企業の活躍が期待されています。
これまでは作るだけで終わっていたものが、「作った後の運転や管理(O&M)」も日本が関わり、長くサポートするやり方に変えていこうとしています。
今後は、現地の人とも協力しながら、日本の技術・アイディアなどを世界に届けられる可能性が高まるでしょう。
土木業界についてのよくある質問Q&A
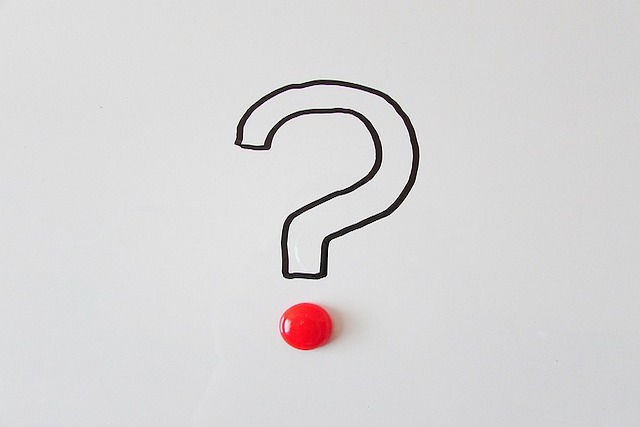
さて、ここからは土木業界で働きたい方が疑問に思うことを、「Q&A方式」で答えていきます。
ぜひ参考にしてみてください。
Q.土木業界は未経験でも働けますか?
A.はい、土木業界は未経験者の採用に積極的な業界です。
多くの建設会社や工務店では、未経験者向けの求人を多数出しており、特別な資格や学歴がなくても現場作業員としてスタートできます。
年齢や学歴による制限も少なく、中卒や高卒から活躍している人も多数います。
未経験から始めて経験を積み、資格取得やキャリアアップを目指すことが可能です。
Q.土木業界の年収はどれくらいですか?
A.土木業界の年収は、職種や経験、資格、地域によって幅があります。
未経験の現場作業員の場合、初年度の年収は300万円前後が目安ですが、経験を積み重ねたり、土木施工管理技士などの資格を取得することで、年収400万円~600万円以上を目指すこともできます。
施工管理や設計職、現場監督などにキャリアアップすれば、さらに高い年収が期待できます。
大手ゼネコンや公共工事を多く手がける企業では、平均年収がさらに高い傾向にあります。
下記の記事では土木作業員の年収を紹介しているので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。
Q.土木業界でキャリアアップするにはどうすればいいですか?
A.未経験からでも、現場で経験を積みながら資格取得を目指すのが、一般的なキャリアアップの道です。
例えば、土木施工管理技士や測量士補、車両系建設機械の技能講習など、段階的に取得できる資格が多数あります。
企業によっては資格取得支援や講習費用の補助を行っているところもあり、働きながらスキルアップが可能です。
将来的には現場管理や設計職、さらに管理職や経営層を目指すこともできます。
Q.土木業界は今後も安定して働けますか?
A.土木業界はインフラ整備や老朽化対策、防災・減災工事など社会的な需要が高く、今後も安定した仕事量が見込まれています。
特に2025年問題(団塊世代の大量退職)以降は人材不足が一層深刻化しており、未経験者でも積極的に採用する企業が増えています。
また、デジタル化や新技術の導入、国や自治体の投資も続いており、長期的なキャリア形成が可能な分野です。
Q.土木業界で取得しておくと有利な資格は?
A.土木施工管理技士(2級・1級)、測量士補、車両系建設機械、小型移動式クレーン、玉掛け、フォークリフトなどの技能講習が代表的です。
設計職を目指す場合は、土木設計に関するCADスキルや建築士資格も有利です。
土木業界の資格については下記の記事で詳しく解説しています。実務経験なしで取れるものもあるので、ぜひ参考にしてみてください。
まとめ:土木業界の将来性を見据えて行動しよう

土木業界は、インフラ更新需要や国の政策支援により、今後も安定した成長が期待されています。
国土交通省や厚生労働省のデータからも、人手不足や高齢化、廃業増加などの課題は明らかですが、ICTやDXなど新技術の導入で現場は大きく変わりつつあります。
2025年には熱中症対策の義務化という新たな法改正も加わり、現場の安全性や働き方改革が一段と進む見通しです。
土木業界でキャリアを築きたい方は、最新動向をしっかり押さえておきましょう。
なお、土木業界での転職や就職を目指す方は、GARDEN-JOBへの登録をぜひご検討ください。
GARDEN-JOBでは、造園・外構・土木職人専門の求人情報を多数掲載しています。
会員登録をすると企業とのメッセージや応募履歴の確認など便利な機能がご利用いただけます。
ぜひこの機会にGARDEN-JOBに登録して、あなたの理想のお仕事を見つけてください。



























