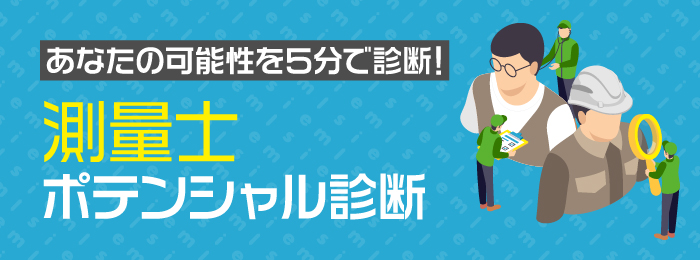「測量士になるにはどうすればいいのだろうか?」
「測量士の資格や仕事内容は?」
「将来性はあるの?」
などと疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
特に、インフラ整備や建設業界に関心がある方にとって、測量士は非常に重要な専門職です。
本記事では、資格取得方法から仕事内容、試験対策、費用、将来性まで、測量士を目指す方に役立つ情報を網羅的に解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。
 目次
目次
測量士とは

測量士は、土地の位置や高さ、面積などを正確に測る職業です。
国や地方自治体、建設会社など幅広い分野で活躍しています。
- 土地開発
- 道路・建物の建設
- 社会インフラ整備
などの基礎を支える役割を担っています。
測量自体は資格がなくてもできますが、一人前の測量士として働くには、国家資格である「測量士」免許の取得が必要です。
測量士の仕事内容
測量士の主な仕事は下記のとおり。
- 地図作成
- 土地境界の確定
- 道路や鉄道、ダムなど建設工事に必要な現地測量作業
- 位置情報のデータ解析
- 設計補助
現場では、GPSやトランシット、レベル、光波測距儀、関数電卓、人工衛星など多様な機器を使用し、2~5人ほどでチームを組んで作業を行います。
現場作業だけでなく、事務所内でのデータ整理や製図作業などデスクワークも重要な業務です。
近年はドローンやCADなどの最新技術が導入され、測量業務の効率化や精度向上が進んでいます。
正確な測量は社会基盤の整備に不可欠。
測量士はインフラや都市計画の現場で、重要な役割を果たしています。
測量士と測量士補の違い
測量士と測量士補はどちらも国家資格ですが、役割に明確な違いがあります。
【測量士】
すべての測量業務を独自に行い、責任者として作業を管理
【測量士補】
測量士の指示・監督下で業務に従事
将来的に独立して活躍したい場合や、より責任ある仕事を目指すのであれば、測量士の資格取得が必須です。
測量士補は測量士の登竜門とも言われ、実務経験やステップアップに役立ちます。
測量士補として現場経験を積みながら、測量士試験合格を目指す方も多くいます。
どちらの資格も建設業界で重宝され、キャリアアップの選択肢が広がります。
測量士になるには

測量士試験には、年齢、学歴、実務経験などの受験資格制限はありません。
測量士になるには、主に3つのルートがあります。
- 国家試験に合格する
- 指定養成施設を卒業し実務経験を積む
- 測量士補からステップアップ
学歴やキャリアプランに合わせて、最適な方法を選ぶことが大切です。
測量士国家試験に合格する
最も一般的な方法は、測量士国家試験に合格するルートです。
高卒で土木会社に就職し、収入を得ながら測量士合格を目指したい方におすすめのルートです。
ただし、測量士国家試験は難易度が高く、広範囲な知識が問われます。
合格を目指すには、計画的に勉強を進める必要があり、数か月から半年程度の準備期間が推奨されています。
費用は受験料や教材費、講座費などがかかります。
過去問の演習や模擬試験を繰り返し、苦手分野を克服することが合格への近道です。
大学・養成施設卒業+実務経験で申請する
指定された大学や養成施設の測量関連学科を卒業し、所定の実務経験を積むことで、国家試験を受けずに測量士資格を申請できる特例ルートもあります。
大学卒業の場合は1年以上、専門学校など養成施設卒業の場合は3年以上の実務経験が必要です。
このルートは、現場経験を積みながら測量の知識や技術を深められる点が大きなメリット。
ただし、費用面で大きな負担になるのがデメリット。
実務を通じて専門性を高めつつ、資格取得を目指す方に適した方法です。
測量士補からのステップアップ
まず測量士補の資格を取得し、その後実務経験を積んで測量士になる方法もあります。
測量士補は測量士よりも試験の難易度が低いです。
測量士補として現場経験を重ねることで、実践的な知識を身につけつつ、測量士試験合格も目指せます。
費用面でも段階的に資格取得準備ができるため、経済的負担を抑えたい方にもおすすめです。
測量士補からステップアップすることで、着実にキャリアを積み上げられます。
測量士は難易度が高いため、不合格になる方も多く、複数回受験する場合は、費用だけ増えてしまいます。
まずは測量士補で基礎を身に着けたい方、確実に1つずつ課題をクリアしていきたい方におすすめのルートです。
測量士試験の詳細
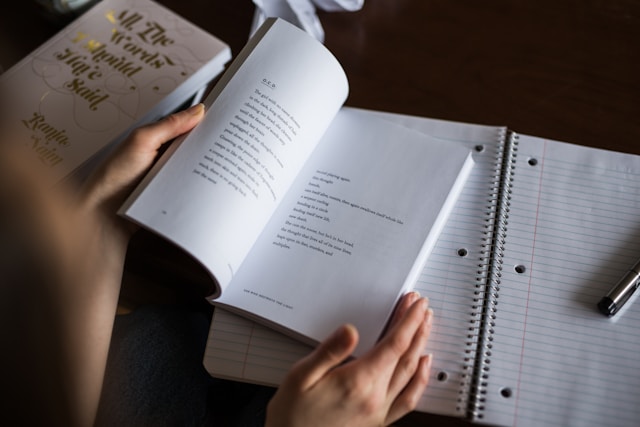
測量士試験は年に1回実施され、筆記試験のみで構成されています。
試験内容や科目、難易度をしっかり理解し、計画的に準備を進めることが重要です。
会場や日程も事前に確認し、万全の態勢で臨みましょう。
測量士試験の内容・科目
測量士の試験科目は下記のとおり。
| 試験区分 | 試験方式 | 出題内容 | 出題数 | 配点 | 解答方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 択一式(5択) | 全分野からの選択問題 | 28問 | 1問25点(700点満点) | 全問解答 |
| 午後 | 記述式 | 必須問題(4問) | 1題(設問数4問) | 300点 | 全問必須 |
| 午後 | 記述式 | 選択問題(各3問)※基準点測量、地形・写真測量、地図編集、応用測量 | 4題中2題(計6問) | 各200点(計400点) | 2題選択 |
合格基準
- 午前:700点満点中450点以上
- 午前と午後の合計:910点以上(1400点満点)
主な試験科目
試験科目は下記のとおり。
- 測量に関する法規及びこれに関連する国際条約
- 多角測量
- 汎地球測位システム測量
- 水準測量
- 地形測量
- 写真測量
- 地図編集
- 応用測量
- 地理情報システム
試験内容は下記のとおり。
| 試験区分 | 試験方式 | 出題内容 | 出題数 | 配点 | 解答方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 択一式(5択) | 全分野からの選択問題 | 28問 | 1問25点(700点満点) | 全問解答 |
| 午後 | 記述式 | 必須問題(4問) | 1題(設問数4問) | 300点 | 全問必須 |
| 午後 | 記述式 | 選択問題(各3問) ※基準点測量、地形・写真測量、地図編集、応用測量 | 4題中2題(計6問) | 各200点(計400点) | 2題選択 |
合格基準は、午前の点数450点以上、かつ午前と午後の点数の合計が910点以上です。
実際の業務に直結する速算力や計算精度、用地測量・地籍調査・工事測量などの応用範囲も問われます。
法律知識だけでなく、現場で役立つ応用技術やトラブル対応の知識も重視されます。
測量士試験の難易度と合格率
測量士試験の合格率は「約10~15%」と低く、難易度は高め。
国家資格の中でも特に難しい部類に入ります。
独学で合格を目指す場合、徹底した勉強スケジュールと自己管理が求められます。
測量士補試験よりも出題範囲が広く、計算問題や法規の正確な理解が不可欠です。
測量士試験の日程と会場
測量士試験は例年5月ごろに実施され、全国各地の主要都市に会場が設置されます。
受験申込期間や会場は国土地理院または試験運営機関の公式サイトで発表されるため、定期的に確認することが大切。
申し込みや会場までの移動には費用や時間がかかることもあるため、早めの計画が推奨されます。
測量士試験の勉強方法
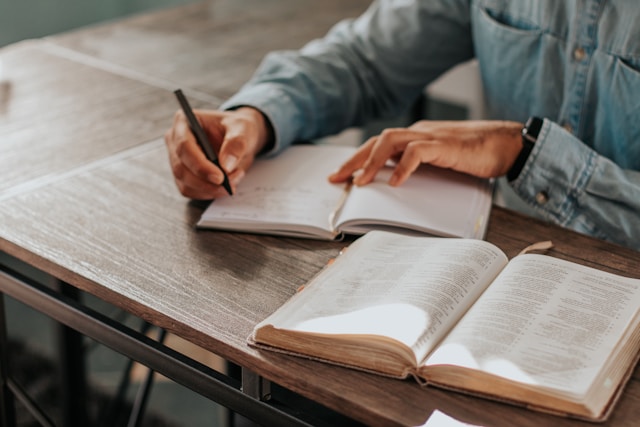
効率的な勉強方法を実践することで、測量士試験の合格がグッと近づきます。
市販の参考書や問題集、通信講座、予備校を活用して知識を定着させることが重要です。
独学と専門講座のメリット・デメリットも理解し、自分に合った学習スタイルを見つけましょう。
おすすめの参考書・問題集
一番のおすすめは、公益社団法人日本測量協会が出版している
- 「測量士・測量士補国家試験受験 受験テキスト」
- 「測量士・測量士補国家試験 科目別模範解答集」
この2つです。
購入方法は、公益社団法人 日本測量協会をご覧ください。
勉強方法はインプットとアウトプットをバランス良く繰り返すことがポイント。
過去問をマスターすれば、確実に合格点以上の点数を取ることができるため、過去問の演習は特に重要です。
ただし、単に過去問を覚えるだけでなく、知識や過程を理解し、応用できる状態にすることが合格への鍵です。
効率的な勉強スケジュール
半年から1年かけて計画的に学習を進めるのが良いでしょう。
最初は基礎知識のインプットに集中し、徐々に過去問演習や模擬試験を増やしていく方法が一般的。
毎週の目標を細かく設定し、得意・不得意分野を見極めて効率よく勉強することが大切です。
モチベーション維持のため、学習仲間との情報交換や、予備校・通信講座のサポートを活用するのも有効です。
計画的な勉強スケジュールを立て、継続的に学習を続けることが合格への近道です。
独学と予備校・通信講座の比較
独学のメリットは費用を抑えられる点と自分のペースで進められること。
一方、予備校や通信講座はカリキュラムや講師のサポートが充実しており、疑問点をすぐに解消できるのが魅力。
合格率が大きく上昇するのが最大のメリットです。
苦手分野の克服や短期集中が求められる場合に、大きな効果が期待できます。
測量士になるための費用

測量士を目指すには、試験・登録費用だけでなく、勉強に使う教材や講座費用、試験当日の交通費など多くの費用がかかります。
資格取得ルートや勉強方法によっても必要な金額は大きく変わるため、事前にしっかり予算立てをしておくことが大切です。
試験費用・登録費用
測量士には試験手数料のほか、登録手数料がかかります。
測量士試験の試験手数料は「4250円」
合格後、測量士としての登録申請時には登録免許税「30,000円」が必要。
その他、証明書類の用意や郵送費など若干の追加費用も発生する可能性があります。
勉強にかかる費用(教材・講座・交通費等)
勉強方法によって費用は大きく異なります。
独学の場合、参考書や問題集に5,000~10,000円程度が目安です。
予備校や通信講座を利用すると、約5万〜10万円以上かかることもあります。
試験会場までの交通費や宿泊費も忘れずに見積もりましょう。
自身のライフスタイルや予算に合わせて最適な勉強環境を整えることが重要です。
測量士のキャリアと将来性

測量士はインフラ整備や都市計画、土地開発の現場などで欠かせない専門職です。
今後も需要が見込まれ、安定したキャリアアップや高待遇が期待できます。
測量士の活躍できる職場
測量士が活躍できる職場は下記のとおり。
- 建設会社
- 測量会社
- 建設コンサルタント会社
- 不動産会社
- 土地家屋調査士事務所
- 官公庁の土木・都市計画部門
など、公共・民間問わず多様な職場で活躍できます。
近年はITやドローン技術を活かした新しい測量業務も増加しており、デジタル化が進む中で活躍の場が広がっています。
技術の発展により、ドローンやAIを活用した測量が普及しつつあり、従来の測量業務が減少する可能性も指摘されています。
しかし、新技術を使いこなせる人材はまだ少なく、ドローン免許やAI活用の知識を持つことで将来性を高められます。
測量士の年収・待遇
測量士の年収は就職先や経験によって幅がありますが、501.6万円程度が相場です。
日本の平均年収(433万円)と比較するとやや高い傾向にあります。
入社して1~2年は200~300万円程度ですが、現場リーダーや管理職になると500万円を超える可能性があります。
資格手当や福利厚生も充実している職場が多く、安定した生活基盤を築きたい方にもおすすめです。
まとめ:測量士になるために今すぐ行動しよう!

測量士は、インフラや街づくりを支えるやりがいのある国家資格です。
資格取得には国家試験合格、指定養成施設卒業+実務経験、測量士補からのステップアップなど複数のルートがあります。
試験は難易度が高く、合格率は10~15%程度ですが、計画的に勉強すれば十分合格を目指せます。
将来性も高いので、興味のある方はぜひチャレンジしてみてください。
なお、造園・園芸・外構・土木職人専門の転職求人サイト「GARDEN-JOB」では、測量士や関連職種の求人情報も豊富に掲載されています。
企業とのメッセージのやりとりや応募履歴の確認など便利な機能も利用できますので、ぜひ会員登録をご検討ください。