「コンクリート診断士ってどんな資格?」
「難易度や合格率はどれくらい?」
「どうすれば合格できるの?」
といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
コンクリート診断士は、建設業界で特にインフラの維持管理や老朽化対策が注目される中、ますます需要が高まっている資格です。
資格取得のメリットや受験資格、難易度、効果的な勉強法まで、合格を目指す方にとって知りたい情報を網羅的に解説しますのでぜひ最後までご覧ください。
造園・外構業界に興味がある方はまずは会員登録から
 目次
目次
コンクリート診断士の仕事内容と資格の概要

コンクリート診断士は、公益社団法人日本コンクリート工学会が認定する民間資格です。
資格取得には、同学会が実施する指定講習会(eラーニング)を受講し、筆記試験に合格した後、登録手続きを経る必要があります
ここでは、コンクリート診断士の仕事内容や詳しい資格概要を見ていきます。
コンクリート診断士の役割と重要性
コンクリート診断士は、橋梁やビル、ダムなどの既存コンクリート構造物の劣化状況を調査・診断し、補修や補強計画を立案する専門家です。
自然災害の多い日本において、建物やインフラの安全性を確保するためには、コンクリートの劣化を正確に評価し、適切な維持管理を行う必要があります。
コンクリート診断士は、構造物の健全性を評価する専門知識を持ち、補修や補強工事の計画を立てることで、社会の安心・安全に貢献しています。
実際、老朽化したインフラが増加している現代では、コンクリート診断士の役割はますます重要になっています。
コンクリート診断士ってどんな資格?
コンクリート診断士は、公益社団法人日本コンクリート工学会が認定する民間資格です。
資格取得には、指定の講習会(eラーニング)を受講し、試験に合格した後、登録手続きを経る必要があります。
講習は基礎編と応用編に分かれており、合計9時間の受講が必要です。
コンクリート診断士試験の内容
コンクリート診断士試験は、以下のような分野の知識と理解力を筆記で問われます。
【試験内容】
- 変状の種類と原因
- 劣化の機構
- 調査手法
- 劣化予測、評価および判定基準
- 対策の種類、補修・補強工法
- 建築物および土木構造物の診断の考え方・調査項目
- 技術および基準類の変遷
【試験形式】
- 四肢択一問題(40問)
- 記述式問題(1000字以内)
コンクリート診断士になるまでの流れ
下記に流れを踏むことでコンクリート診断士になれます。
- eラーニング(講習)を受講する
- 受験資格を満たす
- 試験に合格する
- 登録手続きをして「コンクリート診断士」の資格が付与される
詳しい受験資格については後ほど解説します。
資格取得で得られるメリット
コンクリート診断士の資格を取得することで、就職や転職の際に大きなアドバンテージとなります。
資格手当が支給される企業も多く、収入アップにもつながります。
専門的な知識や技術を身につけることで、現場での対応力や問題解決能力が向上し、キャリアアップの道が広がります。
さらに、コンクリート技士や主任技士などの上位資格の受験資格が得られるため、建設業界でキャリアを積みたい方にとって非常に有益です。
コンクリート診断士の受験資格

試験を受けるには、eラーニングの受講(誰でも受講可能)+受験資格の両方を満たす必要があります。
受験資格は「資格保有」または「学歴+実務経験」のいずれかで得られます
受験資格について詳しく見ていきましょう。
資格保有による受験資格
コンクリート診断士試験の受験資格は、一定の資格を保有している場合に与えられます。
具体的には下記のとおり。
- コンクリート主任技士
- コンクリート技士
- 一級建築士
- 技術士(建設部門または農業部門-農業土木)など
また、実際には上記以外にも
- 土木学会認定技術者(特別上級・上級・1級)
- 建設コンサルタンツ協会認定RCCM(鋼構造及びコンクリート)
- プレストレストコンクリート工学会認定コンクリート構造診断士
- 1級土木施工管理技士または1級建築施工管理技士の監理技術者資格者証
なども受験資格として認められています
この資格を保有している場合、受験年度または前年度に講習eラーニングを受講すれば、試験を受験できるようになります。
出典:2025年度コンクリート診断士講習eラーニングおよび試験のご案内
学歴+実務経験による受験資格
資格を持っていない場合でも、学歴と実務経験によって受験資格を得ることが可能です。
| 卒業した教育機関 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|
| 大学(コンクリート技術科目履修) | 4年以上 |
| 短期大学・高等専門学校(同上) | 6年以上 |
| 高等学校(同上) | 8年以上 |
実務経験は、コンクリート技術関係業務に従事した経験が対象です。
出典:2025年度コンクリート診断士講習eラーニングおよび試験のご案内
受験する際の注意点
コンクリート診断士試験を受験するには、eラーニングの受講が必須です。
講習は2年間有効で、前年度に受講した場合は本年度の受講は免除されますが、前々年度以前に受講した場合は再受講が必要となります。
また、受験資格の証明書類や実務経験証明書の提出が必要な場合もあるため、事前に十分な準備をしておくことが大切です。
申し込みは日本コンクリート工学会の公式サイトから行います。
コンクリート診断士の難易度・合格率

資格取得を目指す方にとって、難易度や合格率は大きな関心事ですよね。
結論から言うと、コンクリート診断士は決して取得しやすい資格ではありません。
この章では、コンクリート診断士試験の難易度や合格率の推移、合格率が低い理由、そして合格を目指す上で知っておきたいポイントについて詳しく解説します。
合格率の推移と傾向
コンクリート診断士は、建設業界でも難関資格として知られています。
合格率は年によって多少の変動がありますが、近年は15%前後で推移しています。
参考までに、下記は2021年から2024年の合格率です。
| 年度 | 合格率 |
|---|---|
| 2024年 | 16.7% |
| 2023年 | 15.7% |
| 2022年 | 16.0% |
| 2021年 | 16.0% |
2割にも満たないとても低い合格率ということが分かるかと思います。
年間約3,000~3,600人が受験し、550人程度しか合格しないケースが多いです。
また、正確な合格基準点は公開されていません。
択一式と記述式の両方で一定の正答率を満たす必要があり、どちらか一方が基準に達していない場合は不合格です。
難易度が高い理由
コンクリート診断士試験の難易度が高い理由は、出題範囲が広く、基礎知識から応用技術まで幅広く問われる点にあります。
択一式だけでなく記述式問題も出題されるため、単なる暗記だけでは対応できず、実務的な理解や応用力が問われます。
専門用語の正確な理解や、誤字・脱字にも注意が必要です。
コンクリート診断士試験の勉強方法と勉強時間
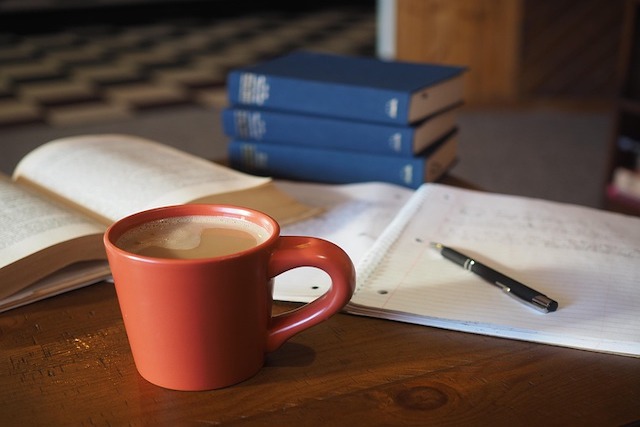
コンクリート診断士試験は高難易度とお伝えしました。
とはいえ、できるだけ1発で合格したいと思うのではないでしょうか。
ここでは、合格するための勉強時間や、効果的な学習方法をお伝えしますので、参考にしてみてください。
推奨される勉強時間
コンクリート診断士試験に合格するためには、十分な勉強時間を確保することが重要です。
人にもよりますが具体的には、試験まで合計300時間程度、約3か月〜6ヶ月の学習期間を見込むと良いでしょう。
特に実務経験が少ない方や、基礎知識に不安がある場合は、早めに学習を開始することが望ましいです。
効率的な勉強法とおすすめ教材
まず過去問を繰り返し解くことが重要。
四肢択一問題はマークシート形式で40問出題され、計算問題も含まれます。
過去問を5周以上解き、全問正解を目指すことで、出題傾向や頻出分野を把握できます。
また、不正解の選択肢について「なぜ誤りなのか」を自分の言葉で説明できるレベルまで理解を深めることが大切。
記述式問題では、診断士の資質や役割、構造物の診断・維持管理に関する基本的な知識が問われるため、要点を簡潔にまとめる練習も必要です。
コンクリート診断士試験に受からない場合
コンクリート診断士試験に受からない場合でも、あきらめる必要はありません。
コンクリート診断士は合格率が低いため、一度で合格するケースが少なく、何度か挑戦して合格している人が多いからです。
試験に受からない場合は、不合格の原因を分析し、苦手分野の強化や記述式問題の対策を重点的に行うことで、次回の合格可能性は大きく高まるでしょう。
また、講習eラーニングの再受講や、実務経験を積むことで、知識の定着や応用力の向上が期待できます。
まとめ:今すぐ始めよう!コンクリート診断士への第一歩

コンクリート診断士は、建設業界で高い専門性と信頼性を証明する難関資格です。
資格取得により、キャリアアップや収入アップ、専門的な業務へのチャンスが広がります。
受験資格は資格保有や学歴・実務経験で得られ、講習eラーニングの受講が必須です。
合格率は15%前後と低いですが、不合格となった場合も原因を分析して対策を練ることで次回の合格につながります。
なお、造園・園芸・外構・土木職人専門の転職求人サイト「GARDEN-JOB」では、造園職人や庭師、外構職人、左官職人、施工管理など、造園・外構業界専門の求人情報をお届けしています。
GARDEN-JOBに会員登録をすると、企業とのメッセージのやりとりや応募履歴の確認など便利な機能がご利用いただけます。
今すぐGARDEN-JOBに登録して、理想の職場を見つけてみましょう。



























