「技術士ってどんな仕事?」
「未経験でも目指せるの?」
「資格取得は難しい?」
と疑問に感じていませんか。
技術士は建設や土木をはじめ、さまざまな分野で活躍できる国家資格です。
この記事では、技術士の仕事内容や資格取得の流れ、試験の難易度、将来性、実際の年収まで、確かな情報に基づいて詳しく解説します。
未経験からチャレンジしたい方にも役立つ内容ですのでぜひ最後までご覧ください。
 目次
目次
技術士とは?役割と仕事内容

技術士試験(一次試験・二次試験)は、文部科学省が所管する国家資格試験です。
試験の実施は、技術士法に基づき指定された、公益社団法人日本技術士会(IPEJ)が担当しています。
日本技術士会は、受験申込の受付や試験運営、合格発表など、試験に関する実務全般を担っています。
社会を支える技術士
技術士は、計画、設計、研究、評価、指導など幅広い業務に携わり、建設・土木・環境・エネルギー・情報通信など多様な分野で活躍しています。
現場の安全や品質の確保、社会インフラの維持管理など、社会の安心と発展を支える重要な役割を果たしています。
専門知識と実践力を活かし、現場の課題解決や品質向上をリードしていく存在です。
技術士の部門一覧
技術士には、以下の21の技術部門があります(2025年7月時点)。
- 機械部門
- 船舶・海洋部門
- 航空・宇宙部門
- 電気電子部門
- 化学部門
- 繊維部門
- 金属部門
- 資源工学部門
- 建設部門
- 上下水道部門
- 衛生工学部門
- 農業部門
- 森林部門
- 水産部門
- 応用理学部門
- 生物工学部門
- 環境部門
- 原子力・放射線部門
- 計量管理部門
- 情報工学部門
- 総合技術監理部門
それぞれの部門で、専門的な知識・技術・実務経験が求められます。自分の専門分野やキャリアに合わせて、受験する部門を選ぶことになります。
技術士が働く現場
建設業の技術士は、建設会社、コンサルタント会社、官公庁、民間企業など、さまざまな現場で働いています。
設計や施工管理、品質管理、技術指導など、現場ごとに役割は多岐にわたります。
技術士補と技術士の違い
技術士補は、一次試験合格や指定教育課程修了後に登録できる資格です。
実務経験を積みながら技術士の指導を受ける立場であり、二次試験合格後に技術士となり、より高度な知識と責任を持つ専門家として活躍します。
技術士になると仕事や生活はどう変わる?
技術士資格取得後は、社内外での評価が高まり、より責任ある仕事を任されるようになります。
例えば、管理者や責任者を任されたり、指導を任されたりなどです。
昇進や転職、独立などキャリアの選択肢が広がるので、年収アップも期待できます。
社会的信頼度が高まることで、やりがいも大きくなるでしょう。
技術士になるために必要な受験資格・経験

技術士を目指すには、まず一次試験(技術士補)に合格する必要があります。
ここで技術士になるために必要な受験資格をお伝えしますので、ご覧ください。
一次試験の受験資格・経験
一次試験は受験資格に制限がありません。
理工系の学生や社会人、異業種からの転職希望者も受験できます。
合格後は技術士補として登録し、実務経験を積みます。
また、下記のような免除制度があります。
【旧制度(平成14年以前)の技術士二次試験合格者の一次試験免除】
| パターン | 基礎科目 | 専門科目 |
|---|---|---|
| 合格した部門と同じ部門を一次試験で受験する場合 | 免除 | 免除 |
| 合格した部門と異なる部門を一次試験で受験する場合 | 免除 | 受験要 |
※いずれの場合も適性科目は受験が必要です。
このように、一次試験で免除される科目は「受験する部門が、過去に二次試験で合格した部門と同じか異なるか」によって異なります。
二次試験の受験資格・経験
二次試験の受験には、一次試験合格または指定教育課程修了後、必要な実務経験を積むことが求められます。
| 実務経験の内容 | 必要な年数 |
|---|---|
| 技術士の指導を受けながら | 4年以上 |
| 監督者の下で | 4年以上 |
| 上記の合計(指導や監督を含む) | 7年以上 |
※いずれか1つを満たせば実務経験要件を満たします。
(例:技術士の指導3年+監督者の下4年=合計7年でも可)
大学院修士や博士課程の研究期間も一部実務経験として認められます。
また、技術士二次試験(第二次試験)には一般的な免除制度はありません。
原則としてすべての受験者が試験を受ける必要があります。
技術士試験の概要

技術士試験は、一次試験と二次試験に分かれています。
一次試験は科学技術全般の基礎知識や技術士としての適性、専門分野の知識を問う筆記試験です。
二次試験は、実務経験をもとにした専門的な知識や応用力、課題解決力を問う筆記試験と、論理的な説明力や技術士としての適格性を評価する口頭試験で構成されています。
合格後は、公益社団法人日本技術士会への登録手続きが必要。
詳しく見ていきましょう。
一次試験の内容
一次試験は筆記形式で、基礎科目、適性科目、専門科目の3つに分かれています。
基礎科目は科学技術全般の基礎知識、適性科目は技術士としての倫理や義務、専門科目は自分が選択した技術分野の知識が問われます。
試験は、マークシート形式(五肢択一式)で行われます。
| 試験科目 | 内容 | 試験時間 |
|---|---|---|
| 基礎科目 | 科学技術全般にわたる基礎知識を問う問題(設計・計画、情報・論理、解析、材料・化学・バイオ、環境・エネルギー・技術など) | 1時間 |
| 適性科目 | 技術士法第4章(技術士等の義務)の規定の遵守に関する適性を問う問題(技術者倫理や関連法令・社会的責任など) | 1時間 |
| 専門科目 | 受験者が選択した1技術部門に係る基礎知識及び専門知識を問う問題(分野例:機械、電気電子、建設など全20部門) | 2時間 |
基礎科目は設計理論、情報ネットワーク、力学、材料、環境など幅広い分野から出題されます。
適性科目は技術士の義務や社会的責任、専門科目は21部門の中から選択した分野の知識が問われます。
二次試験の内容
二次試験は、筆記試験、口頭試験の2段階で実施。
受験する「技術部門」と「総合技術監理部門」で内容が異なります。
筆記試験は下記の内容で行われます。
総合技術監理部門以外の技術部門
| 試験区分 | 内容 | 試験時間 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 必須科目 | 部門全体の専門知識等 | 2時間 | 記述式 |
| 選択科目 | 専門分野の知識等 | 3時間30分 | 記述式 |
必須科目では、受験する技術部門全体に関する幅広い専門知識や応用力、課題を見つけて解決する力が問われます。
社会や現場で起きている問題を多角的に捉え、自分なりの解決策や提案を論理的に述べる必要があります。
選択科目では、より専門的な分野の知識や応用力が求められます。
自分が選んだ分野の現場課題について、専門家として深く分析し、具体的な解決方法や実践的な対応策を示す力が重視されます。
総合技術監理部門の筆記試験
| 試験区分 | 内容 | 試験時間 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 必須科目 | 総合的管理・監理に関する知識 | 2時間 | 記述式 |
| 選択科目 | 専門分野の知識等 | 3時間30分 | 記述式 |
必須科目では、安全管理や社会との調和、経済性、情報管理、人材管理など、総合技術監理に必要な幅広い視点からの課題解決力や応用力が問われます。
現場全体を見渡し、リスクや品質、効率性などを総合的に判断する力が必要です。
選択科目は、他の技術部門と同様に、専門分野の知識や応用力、課題解決力が問われます。
口頭試験(筆記試験合格者のみ)
技術士二次試験の口頭試験は、筆記試験に合格した方だけが受けられる「最終関門」です。
技術士としての適格性等について口述試験により行い、実務経験や論理的な説明力、技術士としての適格性が評価されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 試験時間 | 原則20分程度(実質17~19分のケースが多い) |
| 質疑応答 | 面接形式で試験官2~3名、直接質疑応答 |
| 注意事項 | 3分程度で業務内容説明を求められる場合あり |
技術士二次試験の口頭試験では、業務をやり遂げる力やチームで動ける力、自分の考えを分かりやすく説明できるかが評価されます。
現場で起きた課題をどのように見つけて解決したか、そのときどんな工夫をしたかが大切です。
また、技術者の倫理や社会的責任、常に学び続ける姿勢も見られます。
質疑は、筆記試験の内容や業務経歴書から質問されるので、自分の経験を簡潔かつ論理的に話せるように準備しておくことが重要です。
技術士登録の手続きと注意点
二次試験に合格後は、「公益社団法人日本技術士会本部」に登録申請を行い、登録が完了すると正式に技術士を名乗れます。
申請には必要書類の提出と登録料が必要です。
提出書類や費用の内容は日本技術士会の公式サイトで確認し、最新の様式を使いましょう。
登録後は継続的な学習も求められますので、その点も忘れずに準備しておくことが大切です。
技術士試験の難易度【合格率はどれくらい?】
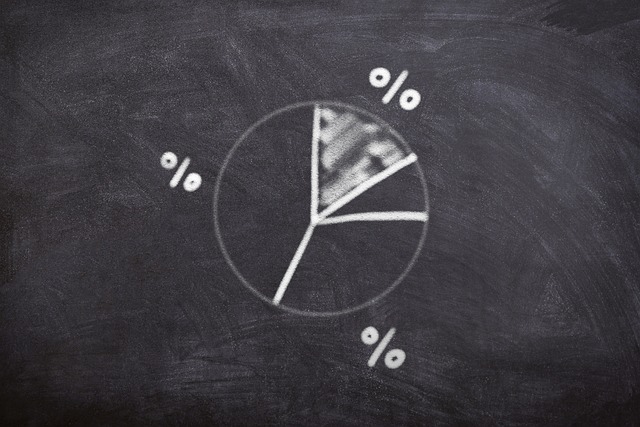
ここまで、試験概要をお伝えしてきました。
本章では、技術士試験の合格率や難易度について解説します。
技術士試験の合格率と難易度
一次試験は基礎知識と応用力が問われ、合格率は30〜50%程度です。
二次試験は記述・口頭試験が中心で、合格率は10%前後と難易度が高いです。
ただし、口頭試験の合格率は80~90%と言われています。
二次試験の記述に合格できれば、口頭試験は5人中4人くらいは合格できることになります。
技術士試験の難易度が高い理由
技術士試験は国家資格の中でも難関です。
専門知識だけでなく、実務経験や論理的思考力、課題解決力など総合的な能力が求められるためです。
受験者は社会人経験者が多いですが、若手や未経験からチャレンジする人も増えています。
一度ではなかなか合格が難しいので、何度かチャレンジしている方が多いようです。
受験者の傾向
技術士試験は20以上の技術部門から選んで受験できるため、受験者のバックグラウンドはさまざまです。
特に以下の分野の受験者が多い傾向にあります。
- 建設部門(土木・構造・都市計画など含む)
- 機械部門
- 電気・電子部門
- 化学部門
- 環境、農業、情報など新興・多様な分野もあり
工学分野の専門的な実務経験を持つ社会人が中心ですが、所属企業や業界による集団受験も見られます。
これまでの受験者は30代~50代の社会人が多く、特に実務経験を複数年積んだ中堅層が中心です。
最近では若手や女性の受験者も増加しています。
技術士になると収入アップやキャリアアップが期待できる

技術士資格を取得すると、年収や待遇の向上が期待できます。
厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、技術士の平均年収は下記のとおり。
| 区分 | 平均年収 |
|---|---|
| 男性 | 6,733,800円 |
| 女性 | 5,732,200円 |
| 男女平均 | 6,233,000円 |
男女ともに全国平均より高い水準となっており、依然として男性が高い傾向ですが、女性の年収も上昇しています。
資格手当や昇進、転職時の評価も高く、独立してコンサルタント業務を行う人もいます。
建設やインフラ分野では特に需要が高いです。経験や勤務先によっては1000万円を超える場合もあります。
資格手当や昇進、転職時の評価も高いと言えるでしょう。
資格を活かせる職場
技術士を活かせる職場は下記のとおり。
承知しました。「プロジェクト」という言葉を使わずに、表を一部修正してご提案します。
| 職場 | 主な仕事内容・役割 | 特徴 |
|---|---|---|
| 建設会社 | インフラや建築の計画・設計・施工管理、品質・安全管理 | 現場の総合管理や技術的指導など中心的な役割 |
| コンサルタント会社 | 調査、計画、設計、評価、技術監理、技術的助言 | 幅広い業務分野で多様な経験・知見を活かして活躍 |
| 官公庁 | 公共事業の企画、工事監理、技術基準の策定 | 社会インフラ整備や政策立案など公共性の高い業務 |
| 自治体 | 地域インフラ整備、施設管理、工事監督・発注 | 地域密着で住民サービスや災害対応にも携われる |
| 大手企業 | 技術開発、新技術導入、品質管理、知財管理、技術投資評価 | 大規模な開発や研究、海外展開も含む幅広い活躍 |
| 研究機関 | 研究開発、実証試験、技術評価、標準化対応 | 最先端技術の創出や社会実装、学術分野での発信 |
承知しました。「プロジェクト」という言葉を使わずに、表を一部修正してご提案します。
| 職場 | 主な仕事内容・役割 | 特徴(ポイント) |
|---|---|---|
| 建設会社 | インフラや建築の計画・設計・施工管理、品質・安全管理 | 現場の総合管理や技術的指導など中心的な役割 |
| コンサルタント会社 | 調査、計画、設計、評価、技術監理、技術的助言 | 幅広い業務分野で多様な経験・知見を活かして活躍 |
| 官公庁 | 公共事業の企画、工事監理、技術基準の策定 | 社会インフラ整備や政策立案など公共性の高い業務 |
| 自治体 | 地域インフラ整備、施設管理、工事監督・発注 | 地域密着で住民サービスや災害対応にも携われる |
| 大手企業 | 技術開発、新技術導入、品質管理、知財管理、技術投資評価 | 大規模な開発や研究、海外展開も含む幅広い活躍 |
| 研究機関 | 研究開発、実証試験、技術評価、標準化対応 | 最先端技術の創出や社会実装、学術分野での発信 |
技術士は、高度な専門知識と実務経験を持つことが認められた国家資格です。
そのため、上記のような職場で専門家としての信用が高まり、取引先や社会からの信頼も得やすくなります。
独立してコンサルタント業務を行う人もいます。
これからの技術士に期待される役割と将来性

社会インフラの老朽化や担い手不足、デジタル化の進展、災害や環境問題への対応など、技術士に求められる役割は今後ますます広がります。
ここでは、これからの技術士の役割や将来性についてお伝えします。
社会インフラの維持・更新で不可欠な存在に
高度経済成長期(1950年代~1970年代)に全国で整備された道路、橋、上下水道、鉄道、港湾などの社会インフラは、現在その多くが築50年以上を迎え、急速な老朽化が進んでいます。
今後20年で、建設後50年以上経過するインフラの割合はさらに増加し、補修や更新の必要性が高まっています。
つまり、これからは大量の老朽インフラを安全・効率的に維持・再生していく社会になります。
そこで、技術士の存在と活躍がより一層重要になると考えられます。
専門的視点と総合的判断力を備えたプロとして、今後ますます技術士への期待と必要性が高まるでしょう。
担い手不足と生産性向上への貢献
建設業界では労働人口の高齢化が進み、若手の担い手不足が課題となっています。
こうした状況で技術士は、高度な専門知識をもとに、若手技術者の育成や実践的な指導を積極的に行うことが求められます。
また、業務の効率化や施工の品質向上を目指して、生産性向上のための工夫や改善を施し、現場への最新技術の導入・普及にも力を発揮しています。
結果として、技術士は現場の人材力と技術力の底上げ、業界全体の発展に不可欠な存在となっており、今後ますます重要性が高まります。
デジタル化・DX推進の重要な担い手
AIやIoT、BIM/CIMなどのデジタル技術が急速に発展するなか、技術士は社会インフラや産業現場のデジタル化をリードする役割を担っています。
DX(デジタルトランスフォーメーション)推進では、単なるITツールの導入だけでなく、業務プロセスや組織体制そのものの変革が求められます。
技術士は、現場で起きている課題を見つけ、その解決のためにAIやビッグデータ、IoT、クラウドといった最新のデジタル技術を実際の業務に取り入れています。
例えば、建設現場ではドローンや3Dモデル(BIM/CIM)を使って設計や進捗管理を効率化したり、センサーやデータ分析を活用して設備の異常を早期に発見したりしています。
災害・環境問題への対応力も求められる
近年は地震や台風、豪雨などの自然災害が大きくなり、気候変動によるリスクも高まっています。
技術士には、災害が起きたときにドローンやAIなどの新しい技術を使って被害状況をすばやく調べたり、インフラの復旧計画を立てたりする役割が期待されています。
また、環境問題への対応も重要。省エネや再生可能エネルギーの導入、環境に配慮した設計や施工、リサイクル技術の活用など、持続可能な社会づくりに貢献することも技術士の大切な仕事です。
多様なスキルとリーダーシップの発揮が重要
技術士には、専門知識や技術力だけでなく、現場をまとめるリーダーシップやコミュニケーション力、問題解決力が求められます。
現場には発注者、協力会社、設計者、地域住民など、利害や考え方が異なる多くの関係者がいます。
技術士は、こうした関係者同士の意見を聞き、納得できるように調整しながら、全体の目標を達成する役割を担います。
また、トラブルや課題が発生したときには、冷静に状況を分析し、最適な解決策を考えて実行する力も必要です。
技術士チャレンジに関するQ&A(FAQ)

ここからは技術士を目指す方が疑問に思うことをQ&A形式でお答えしていきます。
未経験からでも本当に合格できる?
未経験からでも一次試験にチャレンジでき、実務経験を積みながら技術士を目指せます。
多くの人が未経験からスタートし、合格していますよ。
合格までに必要な勉強時間はどれくらい?
技術士試験の合格に必要な勉強時間は、一次試験と二次試験を合わせて1,000~1,400時間程度が目安です。
一次試験(筆記式)は、400時間前後。過去問を中心に基礎知識を身につける勉強が中心で、1日2時間の勉強なら約半年かかる計算です。
二次試験(筆記・口頭)は、約600~1,000時間。実務経験に基づく論文対策や、専門知識の整理、口頭試験の練習などが必要です。
ただし、必要な勉強時間は人によって大きく異なります。
すでに実務経験が豊富な人や基礎知識がある人は、短期間で合格するケースもあります。
一方、専門知識に自信がない場合や独学の場合は、より多くの時間が必要になることもあります
文系出身でも技術士になれる可能性は?
理工系以外の出身者でも、一次試験に合格し、実務経験を積めば技術士を目指せます。
ただし、専門知識の習得や現場経験が必要です。
効率的な勉強法やおすすめの教材は?
過去問の分析や模擬試験、専門書の活用が効果的です。通信講座やオンライン教材も人気があります。
例えば、下記の参考書や過去問があります。
女性技術士はいるの?
女性技術士もいます。
公益社団法人日本技術士会によると、2021年時点で女性会員は352人と、年々増加傾向にあります。
まとめ:技術士で未来を切り拓く!今すぐ一歩を踏み出そう!

技術士は、国の法律に基づく国家資格であり、公益社団法人日本技術士会が社会的地位や資質向上を支えています。
未経験からでも挑戦でき、実務経験を積みながら専門性を高められます。
資格取得後は年収アップやキャリアの幅が広がり、将来性も高い職種です。
自分の可能性を広げたい方は、ぜひ技術士へのチャレンジを検討してください。
なお、転職やキャリアアップを目指すなら、GARDEN-JOBへの登録がおすすめです。
GARDEN-JOBは造園・外構・土木職人専門の転職求人サイトで、会員登録すると便利な機能が利用できます。
新しい一歩を踏み出すなら、今がチャンス!ぜひGARDEN-JOBを有効活用してみてください。
転職なら


愛知県稲沢市生まれ。稲沢市が「日本四大植木産地」であることもあり、幼少期か ら植木に囲まれて成長。
東京農業大学卒業後、名古屋市内の造園会社に就職。 公園の設備工事から国交省事業の国道整備工事における土木及び街路樹等の植 栽工事に現場代理人として携わる。
造園、園芸、外構、土木業界での転職を今すぐ探すなら業界専門の求職サイトがオススメ!


























